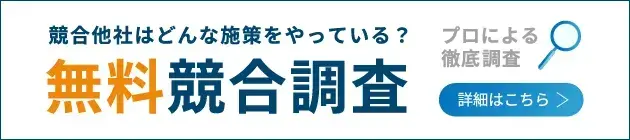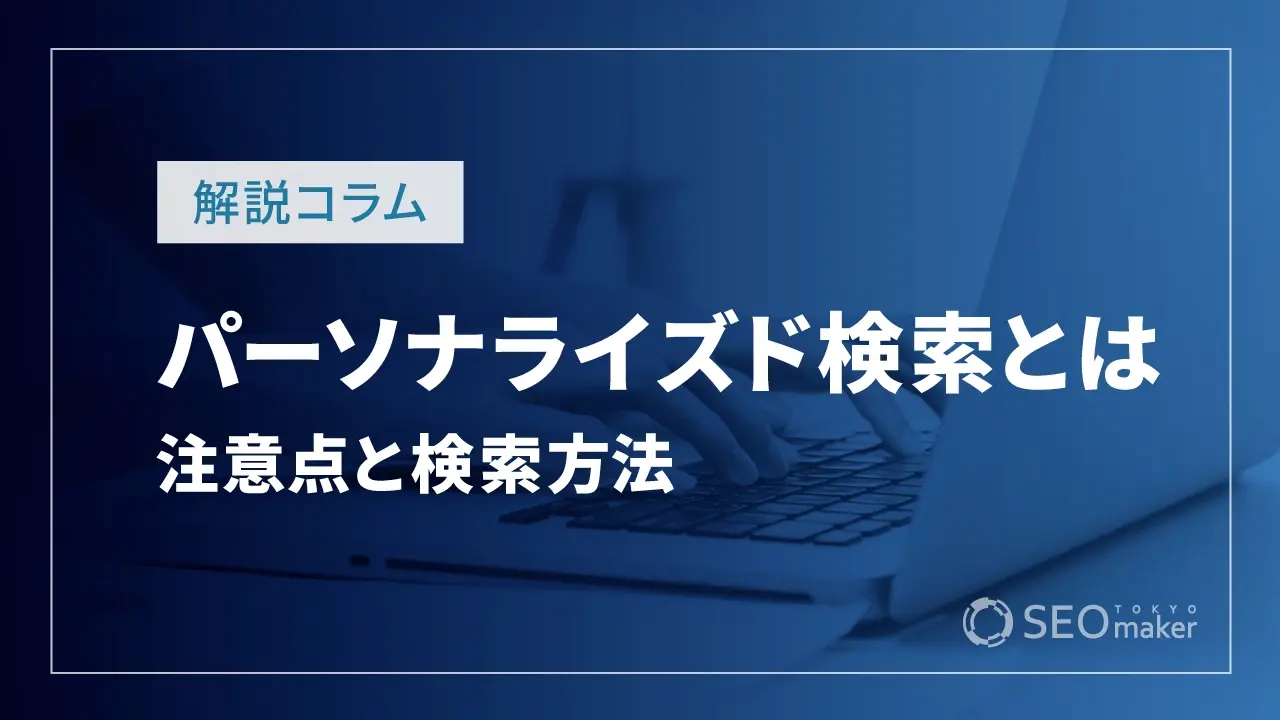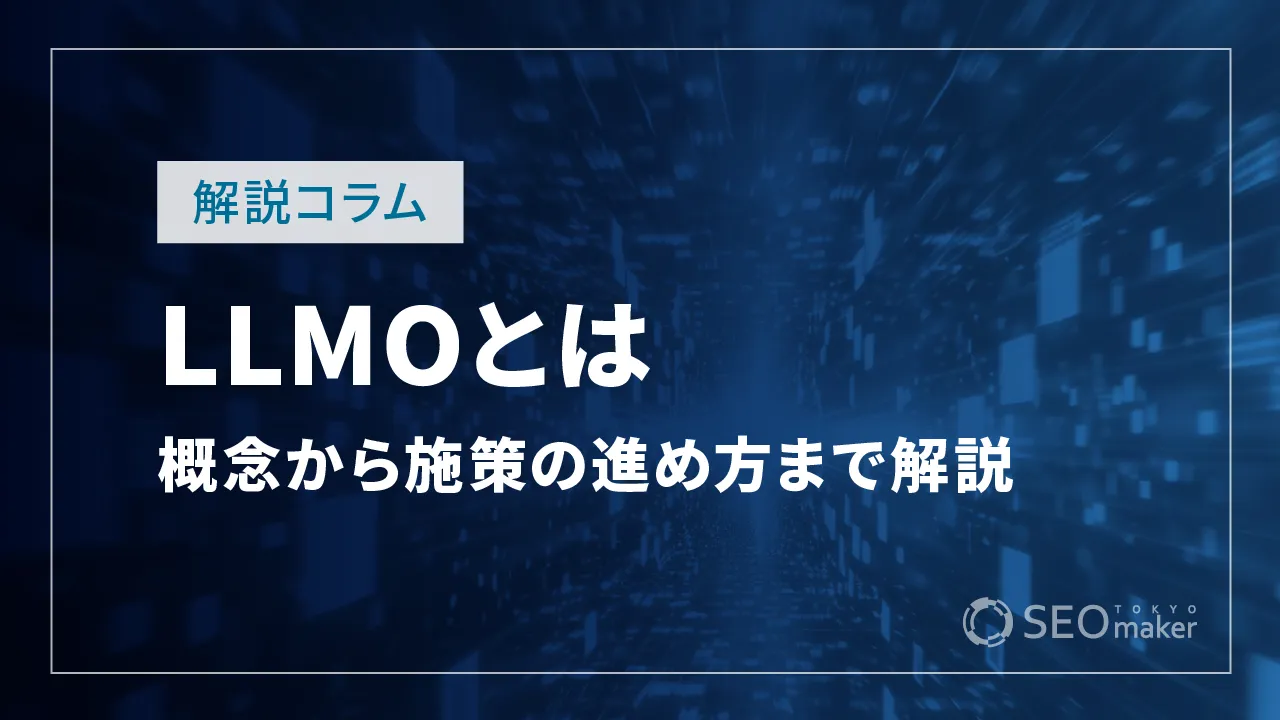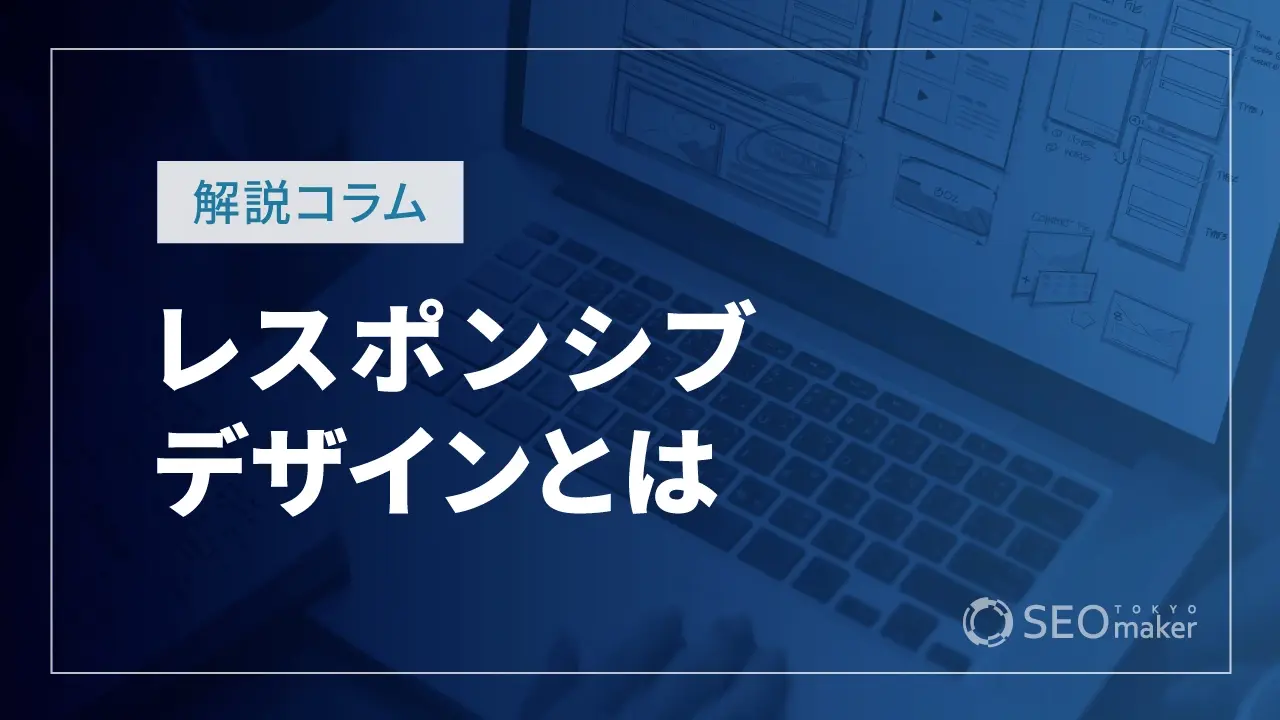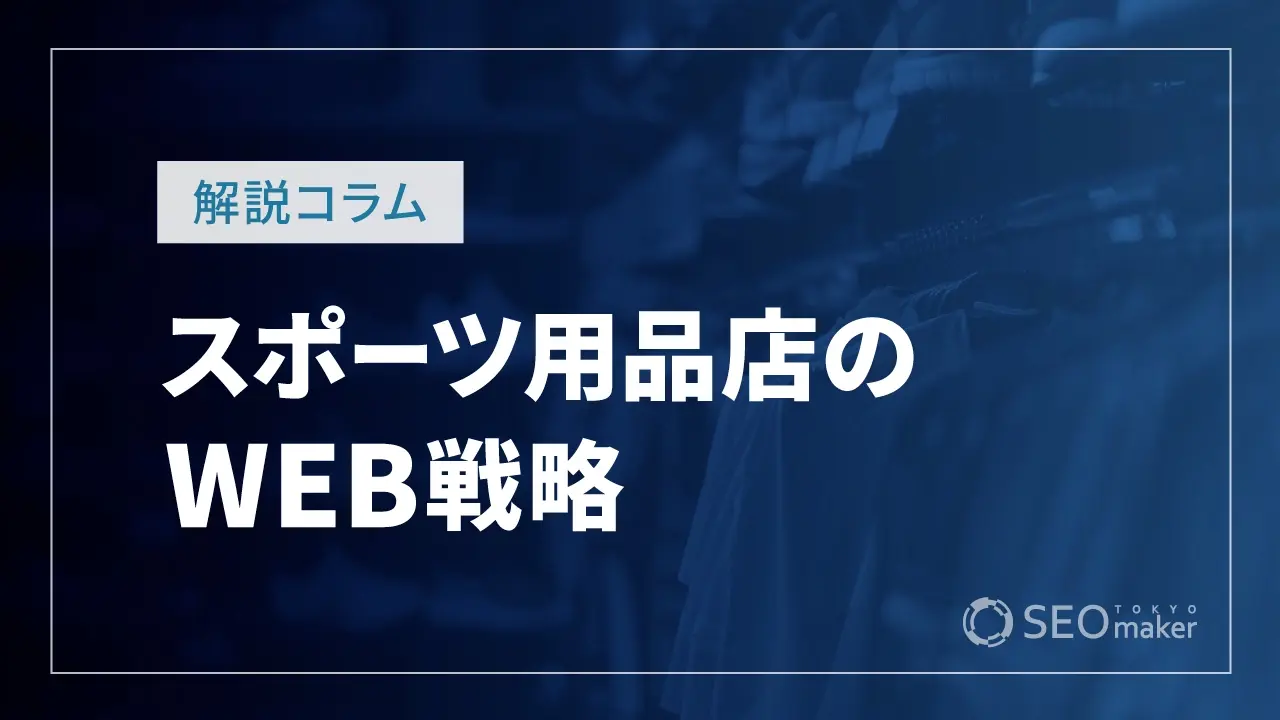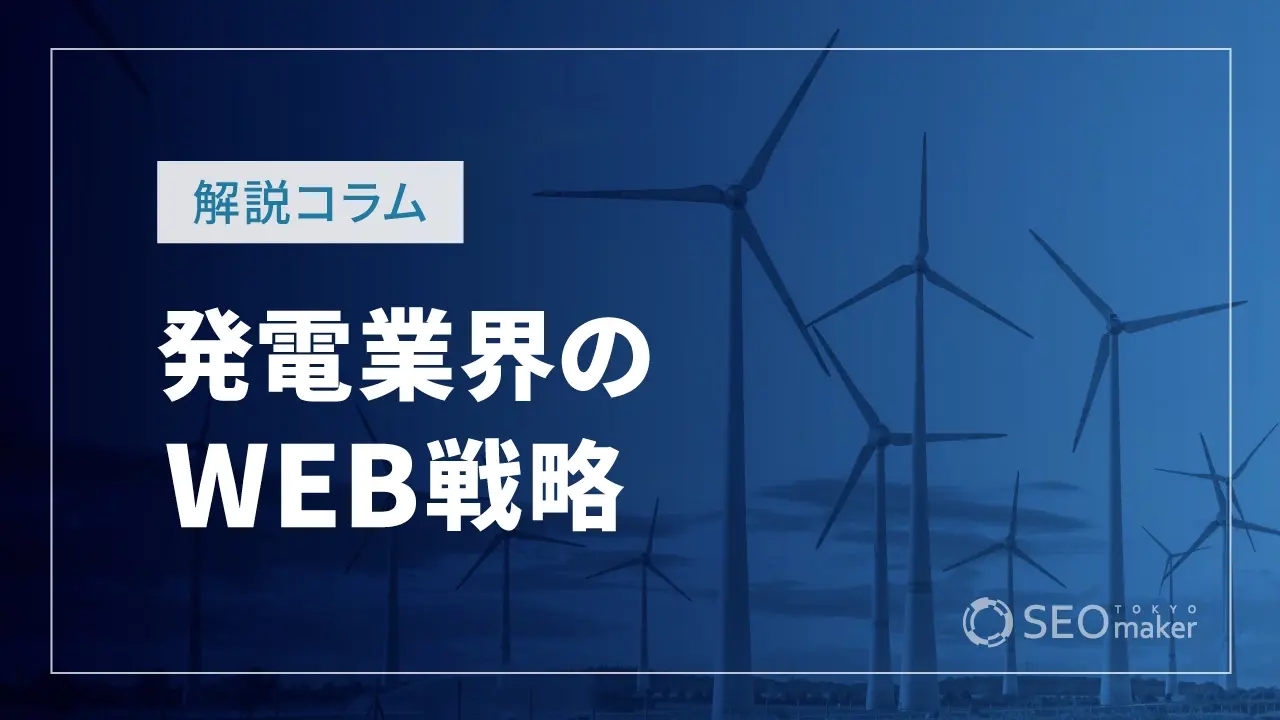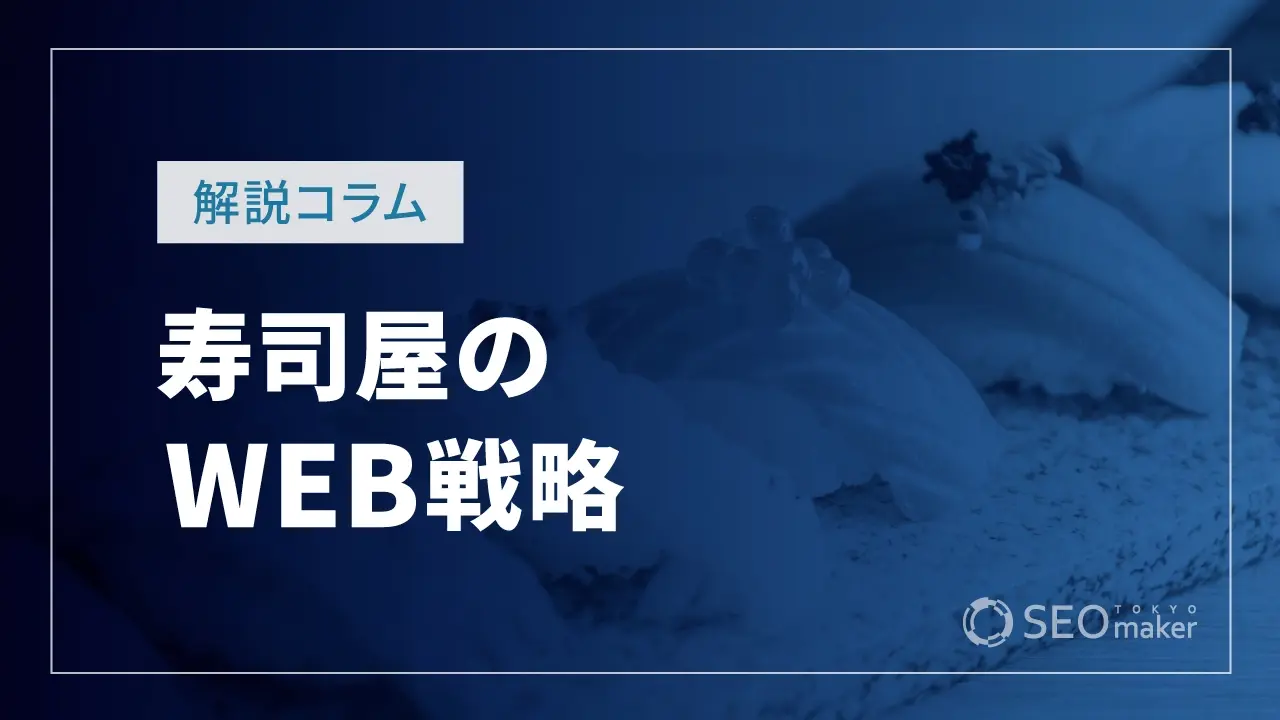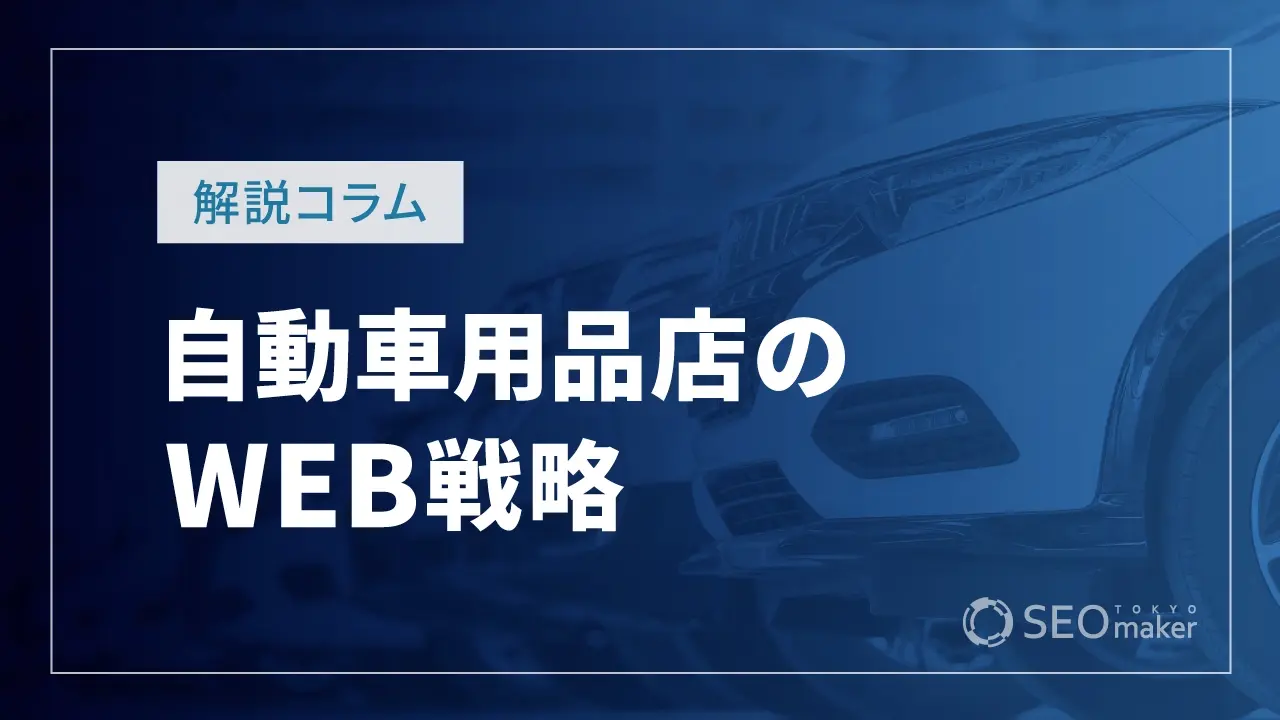PDCAとは?品質管理や社内教育で活かすポイントなど解説
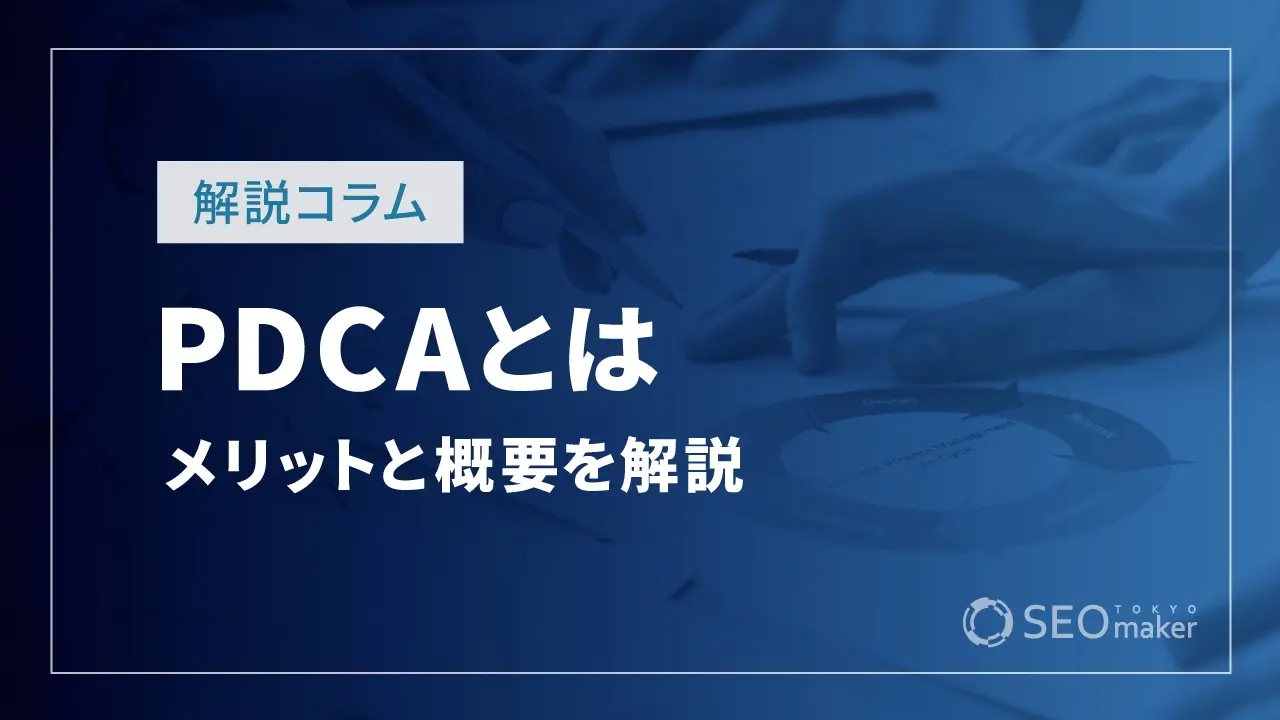
John C. Anderson博士らの調査では、PDCAのようなプロセス改善モデルを導入した組織は、KPI(主要業績指標)が平均17%改善したという報告があります。このような成果は、製造業・品質管理の分野だけでなく、WEBマーケティングやSEO業務でも応用が可能です。
実際、Plan(仮説立案・計画)→Do(実行)→Check(確認・評価)→Act(改善を確定・拡張)というサイクルを繰り返すことで、SEO対策の精度を高めていくことができます。そこで、PDCAの基本とメリット、SEOは業務などにおける具体的活用法など詳しく解説します。社内プロジェクトやWEBマーケティングなどに取り組む際に、今回お伝えするPDCAサイクルをぜひ活用ください。
PDCAとは
PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)とはプロジェクトを継続的に改善するための4段階のモデルです。このサイクルを何度も繰り返すことによって、プロジェクトを遂行する際の質を高めることができます。PDCAは、ウォルター・A・シューハートによって開発され、のちにW.エドワーズ・デミング博士によって普及したため、「デミング・サイクル」や「シューハート・サイクル」とも呼ばれます。それでは、各ステップごとの詳細について、詳しく解説します。
Plan
PDCAサイクルの最初の段階はPlan(計画)です。プロジェクトの目標を決定し、その目標を達成するために必要な変更点や計画を検討するステップです。例えば、マーケティングチームがオンライン広告の効果を向上させようとした場合、Planフェーズでは、どの箇所に課題があるのかやテスト期間、使える予算などの計画を立てます。
注意点としては、闇雲にプロジェクトの目標を立てれば良いわけではなく、組織のミッションや価値観と合致していることも考慮してください。部分最適を図るのではなく、全体最適を目指す必要があります。
Do
2番目の段階であるDo(実行)は、計画されたことをテスト的に実行に移すステップです。例えば、マーケティングチームがオンライン広告の効果改善を図る場合、Doフェーズでは、代替の見出しを使用したA/Bテストを実施したり、広告にかける予算を変更したりなどを小規模に進めます。
注意点としては、いきなり大きな行動をとらないことです。PDCAサイクルは、小規模な改善を積み重ねて質を向上させることがポイントです。なるべく早く結果を出したいと思ったら、より慎重に進めるようにしてください。
Check
3番目の段階であるCheck(確認・評価)は、Do(実行)でおこなわれたテストに対しての結果をレビューします。例えば、マーケティングチームがA/Bテストをおこなった場合、Checkフェーズでは、オンライン広告の結果を分析し、新しい見出しが元の見出しよりもリード獲得において何パーセント変化したかを評価します。このように、Doのフェーズでは、期待された結果と実際の結果を比較することで、目標が達成されたかどうかを判断します。
Act
最終段階であるAct(処置・改善)は、先行するCheck(確認・評価)でえられた知見に基づいて標準化や防止策を進めることです。具体的には、もしテストが成功し目標が達成された場合、その新しい方法がチームに定着するようにします。一方、テスト結果が期待を下回った場合、改善策を考えたうえで次のPlanで同じ間違いをしないようにします。
例えば、マーケティングチームが、新しい見出しが元の見出しよりも優れていると判明した場合、チームは今後、他の広告にもその新しい見出しを使用するという行動を起こします。逆に期待を下回っていた場合は、原因と防止策を考え、それを次の段階であるPlanに引き継ぎます。
PDCAのメリット
PDCAの利点を一言でいうと「行動のやりっぱなしを防ぐことができる」ことです。そして、それこそがビジネスの成長を支える秘訣でもあります。ここでは、PDCAのメリットをわかりやすく解説します。
継続的に改善できる
PDCAサイクルの利点は、一度導入すれば、その後は継続的に運用と改善を繰り返すことが可能な点にあります。特に、PDCAのAct(処置・改善)フェーズでは、成功した変更を標準化させたり、不十分な方法が是正されるため、継続的に改善がおこなわれます。つまり、時間を経るほど無駄の削減や生産性の増加につながります。
データに基づいて決断できる
データに基づいた意思決定ができるのも、PDCAサイクルの利点です。PDCAでは繰り返しテスト的な試みをおこない、従来の方法と結果を比較するため、データから結論を導くことができます。
具体的には、Do(実行)で小規模なテストを実施し、その後に続くCheck(確認・評価)で、収集されたデータを評価・分析し、新しい知見を取り入れます。このように、PDCAは、推測ではなくデータに基づいた改善ができるため、PDCAサイクルを繰り返すほど効果性が高くなります。
関連記事:データドリブンとは?概要やメリット、実践プロセスなど解説
リスクを抑えた進行
PDCAサイクルはリスクを低く抑えながら、プロジェクトを進めることができます。Do(実行)の段階では、小規模なテストを実施しながら進めるため、考案された変更が望ましい結果を達成するかどうかを慎重に検証しながら進められます。もし考案された変更点が効果がない場合でも、それを広く実施した場合より、リスクを大幅に下げることができます。このように行動のリスクを最小限に抑えつつプロセスを改善できるのは、大きなメリットといえます。
PDCAのデメリット
PDCAサイクルは継続的な改善を目指す手法です。そのため、各サイクルは短期的な結果に焦点をあてています。逆に言えば、PDCAだけで業務を遂行するのは、長期的視点が欠けてしまう可能性があります。
例えば、家電メーカーA社がPDCAサイクルで冷蔵庫の生産をしているとします。PDCAサイクルを回すことで、コストを下げ、製品の微調整を繰り返します。結果としてA社は生産性を最大限高めることができます。
しかし一方で、市場ではIoT化した冷蔵庫があふれ、旧来の冷蔵庫を生産し続けたA社の売上が下がるなどのことが考えられます。このように効率や効果性を高めていくPDCAサイクルに取り組むだけでは、中長期的な市場の変化に対応できないことがあります。
PDCAを各業務に活かすポイント
PDCAサイクルの使い方をより実践的に学んでもらうために、SEOなど代表的な業務を挙げ、どのように「Plan・Do・Check・Act」の手順を進めていくか解説します。具体的な業務フローがイメージできるので、自社でもPDCAを導入しやすくなります。
SEO業務
SEO業務にPDCAサイクルを活用することができます。SEOはWEBマーケティングにおいて主要な集客方法の1つであるため、小規模なテストを繰り返し、時間をかけて施策の質を向上させることがポイントです。まず、Planフェーズでは、ターゲットキーワード分析を実施したり、競合調査をおこないます。また、流入数や検索順位などにおいて、 KPI(主要業績評価指標)を決めます。
そして、行動計画を策定し「誰が何をすべきか」また「いつまでに完了すべきか」なども決めます。Doフェーズでは、その計画を実行に移しますが、リスクを最小限に抑えるため、小規模なテストとして実施します。いきなり大きな行動をとれば、それだけリスクが高まるからです。
Checkフェーズでは、テストの結果を評価し、当初の計画や期待された成果と照らし合わせて検証します。例えば「検索順位に及ぼした影響」や「インデックスされたページ数」などに開きがないかを確認してください。最後はActです。もし変更が成功し、設定した目標が達成されている場合は、SEO対策の社内マニュアルに新しい知見を加え、その施策をSEO業務全体に広げていきます。
品質管理
品質管理にPDCAを活かす重要なポイントは、Checkの精度を高めることです。PlanやDoがどれほど丁寧でも、評価が曖昧では改善の方向性を誤ってしまうからです。Checkフェーズでは、感覚ではなくデータに基づいて結果を分析し、設定した品質目標との差を数値として把握することが必要です。
例えば、不良率やクレーム件数、納期達成率などの具体的な指標をモニタリングします。この精度の高いCheckがあれば問題の兆候を早期に発見できるため、品質管理を目的としたPDCAが好循環に入りやすいです。
社内教育
社内教育にPDCAサイクルを活かす場合の重要ポイントは、データに基づいた意思決定をおこない、指導方法の有効性を高めることです。多くの場合、社内教育は担当者の主観や感覚に基づいて実施されているため、PDCAでえられた知見を活かすことが必要です。
まず、Planフェーズでは、従業員のニーズを分析し、教育の目的を決定します。目標達成度を測る客観的な数値も設定してください。Doフェーズでは、指導に関与するすべての担当者に周知し、指導プロセスで発生した洞察やデータを記録します。ここで記録をとっておかないと、後々の改善が図れないので注意してください。
Checkフェーズでは、収集したデータ(例:テスト結果や従業員のフィードバックなど)を分析し、当初の目標と成果を照らし合わせて効果を検証します。どこが成功し、どこに改善の余地があるのかを特定してください。最後にActフェーズでは、検証結果に基づき、教育プロセスや指導法の修正をしたり、標準化したりします。継続的にこれを続けることで、従業員のスキルアップが図られ、生産性向上につながります。
PDCAを効果的に回すポイント
PDCAは誤って理解している人も多く、効果のない枠組みになってしまっているケースもあります。そこでここでは、このPDCAを効果的に回すポイントを紹介します。
数字で目標を決める
PDCAを回して業務を遂行する際には、誰がいつ確認してもわかるように進捗状況や成果を数値化します。また、ゴールの達成までの期日も決めるようにしてください。
このように数値で決めておくと、CheckやActionの段階に入ったとき客観的に確認しやすく、具体的な行動改善などにもつながりやすいです。
具体的な目標の決め方として、良い例と悪い例は次の通りです。
- 次の3ヶ月で売上を110%に向上させる(○)
- 売上をできる限り上げる(×)
「次の3ヶ月で売上を110%に向上させる」は期日や目標数値が入っているため、そのために何をすればよいのか行動計画を立てやすいです。一方「売上をできる限り上げる」は、どこまで売上を向上させれば良いのか分かりません。
Doを記録する
Doの状況を細かく記録するようにしてください。そうすることで、Cehckの段階でPlanの達成率を検討しやすいです。
例えば、Planの段階で、商品の生産性を20%アップさせるということを目標としているとします。そして、Doのところで実際の商品の生産性を記録しておけば、どの日が目標を達成していて、どの日に生産性が下降したのかを正確に掴むことができます。
このように、Doの段階では業務を遂行しながらも同時に結果を記録することを忘れないようにしてください。
PDCAが失敗する要因
PDCAを導入していても、失敗することは多々あります。ここでは、このPDCAの各ステップにおける失敗要因についてお伝えします。
Planの失敗要因
Planのステップでよくある失敗は、高すぎるゴールを設定することです。ゴールが高すぎると、そもそもどう行動をとってよいのか判断できないという状況に陥り、先に進むことができません。
また、仮にPDCAサイクルを開始したとしても、目標と結果の差異が大きすぎて、打てる手段が限られてしまいます。そのため、Planの段階で現実的なゴールを設定する必要があります。
Doの失敗要因
Doのステップでよく起きる失敗要因は、見える化が不十分なことです。Doの行動記録が不明瞭な場合、現状把握ができません。
そのため、行動記録を書く際には漠然とした事実ではなく、より解像度の高い事実を記述するようにしてください。できれば、数値と文章の両方を記録する必要があります。
Checkの失敗要因
CheckはPDCAサイクル全体の中で、もっとも壁にぶつかりやすいポイントです。よく起きる失敗要因は、振り返り自体をおこなわないというものです。
多くの人はどちらかというと新しいことを好みます。新しいPlanを立てれば気分もポジティブになるからです。そして、Doも比較的モチベーションを保ちやすいです。
しかし、Doの後で結果を真正面から受けとめ、チェックをするというのは面倒くささがあり、気分もネガティブになりがちです。結果としてPlanとDoだけを進め、その後なにもせず「やりっぱなし」ということが頻繁に起こるので注意してください。
Actionの失敗要因
Actionのステップでは、修正するための視点を持ち合わせていないという点が挙げられます。問題点や原因が分かっても、どう修正すればよいのか見当がつかないのです。
そこで、Actionの段階では次のECRSというフレームワークを思い出してください。ECRSとは、下記4つから構成されています。
- Eliminate(排除)
- Combine(結合と分離)
- Rearrange(入れ替えと代替)
- Simplify(簡素化)
Eliminateとは、問題の原因になっていることを排除するという視点です。Combineは別のもの同士を結合させたり、元々1つのものを分離したりします。
Rearrangeは、別のものへの置き換えをすることで改善を図ります。Simplifyは、手順を減らしたり、省略することによってシンプルにします。
PDCAサイクル全体を見通し、ECRSの視点で修正できないか検討してください。
PDCAの注意点
PDCAサイクルは効果的な改善手法ですが、使い方を誤ると成果が出ないどころか、時間や労力を浪費することもあります。特に、計画に時間をかけすぎることや緊急対応に適用してしまうなどのミスは多くの現場で起こりがちです。そこで、PDCAを正しく機能させるために押さえておくべき注意点を解説します。
計画段階で完璧を求めない
Plan(計画)フェーズの注意点として、完璧主義になりすぎないようにしてください。このPlanフェーズは、問題の特定、KPI(重要業績評価指標)の設定、行動計画の策定などをおこなうため、最も労力がかかる段階です。しかし、ここであまりにも細部にこだわり、最高の計画を立てようとすれば、何も前に進まず立ち往生してしまう可能性があります。PDCAは反復的なサイクルで、実際の行動を通して知見をえて質を改善していくものなので、行動に移すタイミングを見失わないようにしてください。
緊急性の高い問題に使わない
PDCAサイクルは、継続的に繰り返すことで物事を前に進めると同時に質を改善するプロセスです。そのため、緊急性の高い問題の解決には適していません。PDCAは、Planで問題を定義し、仮説を立て、次にDoで小規模なテストを実施し、その後Checkで結果の分析と評価をおこなうといった段階的なプロセスを踏みます。そのため、目に見える成果をえるまでに時間がかかることが多いです。そのため、緊急性の高い課題に対しては別のモデルを使うようにしてください。
PDCA以外の関連フレームワーク
PDCAと併用して使用することで、効果を高めることができるフレームワークがあります。そこでここでは、PDCA以外のフレームワークをお伝えします。PDCAに慣れてくれば、次の段階として導入を考えてください。
OODA
OODAは、Observe(観察)、Orient(判断・分析)、Decide(決定)、Act(行動)の4つのステップで構成されるフレームワークです。主に意思決定をおこなう際に使用されるものです。
PDCAサイクルと併用して使用することで、多角的に業務を遂行することができます。以下、各ステップについて解説します。
Observe(観察)
今の状況を観察します。情報を収集し、その情報がこれ以降のステップの元となります。また、動きがあるものについては、継続的な観察をおこなう必要があります。
Orient(判断・分析)
前段階の観察を経て分析します。メリットやデメリット、弱点や強みなどを中心に分析します。分析結果は、数値や文章で記述します。
Decide(決定)
分析にもとづいてどのような行動をとるか決定します。決定には計画を含みますが、目的を達成するための最短ルートを考えることが多いです。
Act(行動)
決定された計画にもとづいて実際の行動をとります。行動中や行動後は、効果や成果を確認し、新たな情報をもとに次のサイクルに進みます。
以上がOODAについての概要です。元々は軍事戦術において考案された方法ですが、現在ではビジネスやスポーツなどさまざまな分野に活用されています。
SMART
SMARTとは、目標設定のフレームワークです。次の5つの視点を満たした目標を設定することで、実現の可能性を高めることができます。PDCAでは、Planの段階で活用します。
Specific(具体的に分かりやすい)
目標を設定するときには具体的でなければいけません。漠然とした目標は、好ましくありません。
Measurable(測定可能)
目標は数値で明確にする必要があります。例えば「次回キャンペーンで売上を30%アップする」などのように決めます。
Achievable(達成可能な)
数値が明確でも「売上を10倍にする」などのように、実現不可能なものを設定してはいけません。使える時間や労力、資金などを踏まえて、現実的な目標を設定します。
Result-oriented(結果重視の)
目標が実現したら、その結果は社内や自分にとってプラスになることが大切です。目標を達成しても自分や会社にとってプラスにならない場合、その目標は適切ではありません。
Time-bound(期限)
いつの期限までに目標を達成するのかを決めます。無期限だと、モチベーションを保てないので注意してください。
GTD
GTDは、普段の仕事の効率化に役立ちます。PDCAサイクルでいえば、Doの段階で活用します。GTDは、米国のコンサルタントデビッド・アレンが提唱したもので、具体的には次の手順です。
収集
今日やるべきことや気になっていることを全て書きだします。具体的には、Todoリストをノートに書き出します。
処理
書き出した項目について、仕分けのルールを決めます。例えば「複雑そうなアクションは分解してリスト化する」、「1分以内で完了することは、すぐに実行する」などのことです。
整理
作ったリストを使い慣れた手帳などに整理して記述します。
レビュー
自分が置かれている状況や中期的な予定などを把握し、今できること、すべきことを判断します。
実行
優先順位の高いものから行動に移します。
この5つのステップを繰り返すことで、日々の業務を効率的に進めることができます。
PDCAのよくある質問
ここでは、PDCAサイクルについてよくある問題を取りあげ解説します。実際の業務で導入する際には、これらの注意点を踏まえて進めてください。
Q.Actの実施は現場だけで進めても良いですか?
Answer)Actは再発防止と標準化の2つを考える必要があります。改善や再発防止は現場を中心に進めていきます。一方で標準化(仕組み化・教育・マニュアル整備)は現場ではなく、組織レベルのActです。それぞれの役割分担をすることがポイントです。Actフェーズでえられた知見を個人の改善で終わらせず、組織学習に反映できるかどうかが、PDCAの効果性を決めます。
Q.AI時代にPDCAはもう古いのでは?
Answer)AI時代には、PDCAをAIと人間で役割分担して進めることが重要です。確かに、AIはデータ収集・分析(Check)をするのには長けていますが、PlanとActの質的判断は依然として人間の役割です。AIはPDCAのスピードを加速させてくれますが、その分、人間が「何を改善すべきか」「どんな価値を目指すか」を慎重に決めるようにしてください。このように役割分担することで、PDCAの質そのものを変えることができます。
Q.PDSAとは何ですか?
Answer)PDSAとは「Plan(計画)→Do(実行)→Study(学習・検証)→Act(改善)」の4段階からなるサイクルのことです。これは、PDCAの発展形としてW・エドワーズ・デミング博士が提唱した手法です。PDCAとの違いは、Checkの代わりにStudy(学習)がおかれている点です。単に結果を点検するのではなく、「なぜその結果になったのか」「どんな学びがえられたのか」を深く考察することを重視しています。そのため、PDSAは、プロジェクトや品質管理の向上だけでなく、組織のイノベーションにつながることがあります。
Q.デミング博士がCheckをStudyに置き換えた理由は?
Answer)デミング博士は、Checkが点検や合否判定になってしまいやすいという点を懸念していました。そして、博士は「学習する組織・文化」を目指したため、「Study」に切り替え、データの意味を考察する重要性を説いています。このように、PDSAは「学ぶ組織・チームのため」というニュアンスが大きいです。
Q:PDCAはどのような状況で使用しますか?
Answer)PDCAは主に品質管理などの分野で使用されることが多いですが、大半の業務で使用可能です。それほど汎用性の高いフレームワークです。例えば、部署内で何かのプロジェクトを遂行したい場合もこのPDCAが役立ちますし、WEBマーケテイングのSEOや広告運用などの場面でも役立ちます。
Q: PDCAサイクルにおいて注意すべきポイントは?
Answer)もしPDCAサイクルをチームで取り組む場合、情報を共有する事が大切です。例えば、Planの段階ではチームメンバー全員がその目標や計画を把握する必要があります。全員が目標や計画を把握していなければ、業務を遂行しようとしても、それを何のためにやっているのか理解できず、ミスや誤解が生じかねません。
Q:PDCAサイクルを実施する上で難しい部分は?
Answer)困難な箇所はケースバイケースですが、データの収集と分析は多くの人がつまずきやすい点です。事前に、どのようなデータを収集するのかを決めておかなければ、CheckやActionの段階で状況を客観視することができません。何のデータをとれば改善に結びつくのかを事前に十分検討してください。
Q: PDCAのゴールは何ですか?
Answer)PDCAのゴールはPlanで立てた目標を達成することです。しかし、これを読んでいるあなたは、もう一歩先を見据えることも覚えておいてください。それは仕事の型をつくることです。この型を作ることで、人員が変わったり新しい支店ができても、いつでも再現できるからです。PDCAサイクルが確立すれば、それが会社の資産となります。
まとめ
 PDCAサイクルは、単なる業務改善の手法ではなく、「学びながら成長する組織文化」を育てるための考え方です。Plan(計画)で仮説を立て、Do(実行)で試し、Check(評価)で検証し、Act(改善)で定着させる。この循環を続けることで、チームは失敗を恐れず、データをもとに柔軟に進化していくことができます。特にSEOやWEBマーケティングなど変化の激しい分野では、PDCA導入の有無が差を生み出します。完璧を求めず小さく始め、結果を見て修正するというこの「回し続ける力」こそが、プロジェクト成功の鍵となります。
PDCAサイクルは、単なる業務改善の手法ではなく、「学びながら成長する組織文化」を育てるための考え方です。Plan(計画)で仮説を立て、Do(実行)で試し、Check(評価)で検証し、Act(改善)で定着させる。この循環を続けることで、チームは失敗を恐れず、データをもとに柔軟に進化していくことができます。特にSEOやWEBマーケティングなど変化の激しい分野では、PDCA導入の有無が差を生み出します。完璧を求めず小さく始め、結果を見て修正するというこの「回し続ける力」こそが、プロジェクト成功の鍵となります。