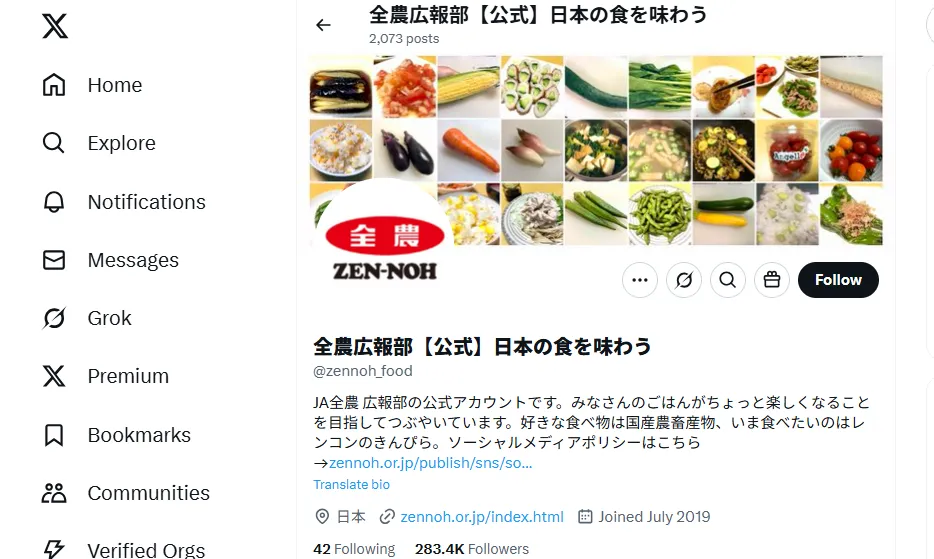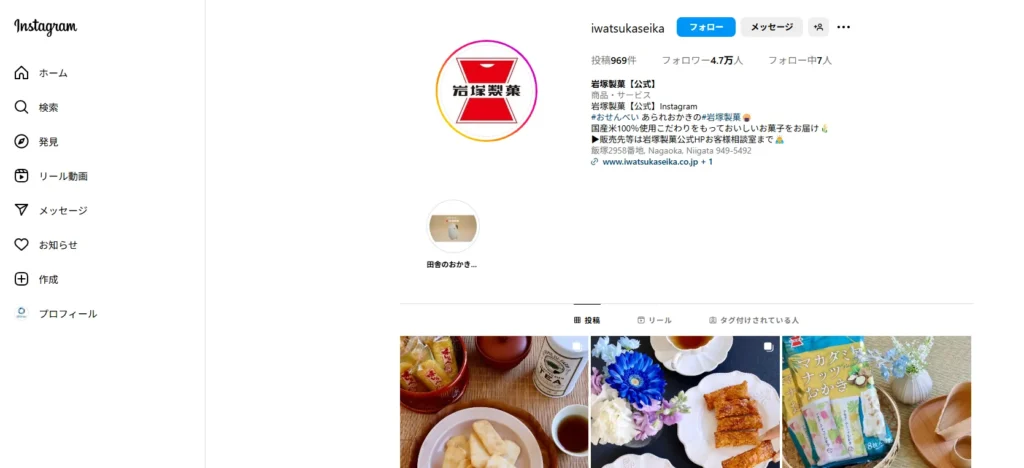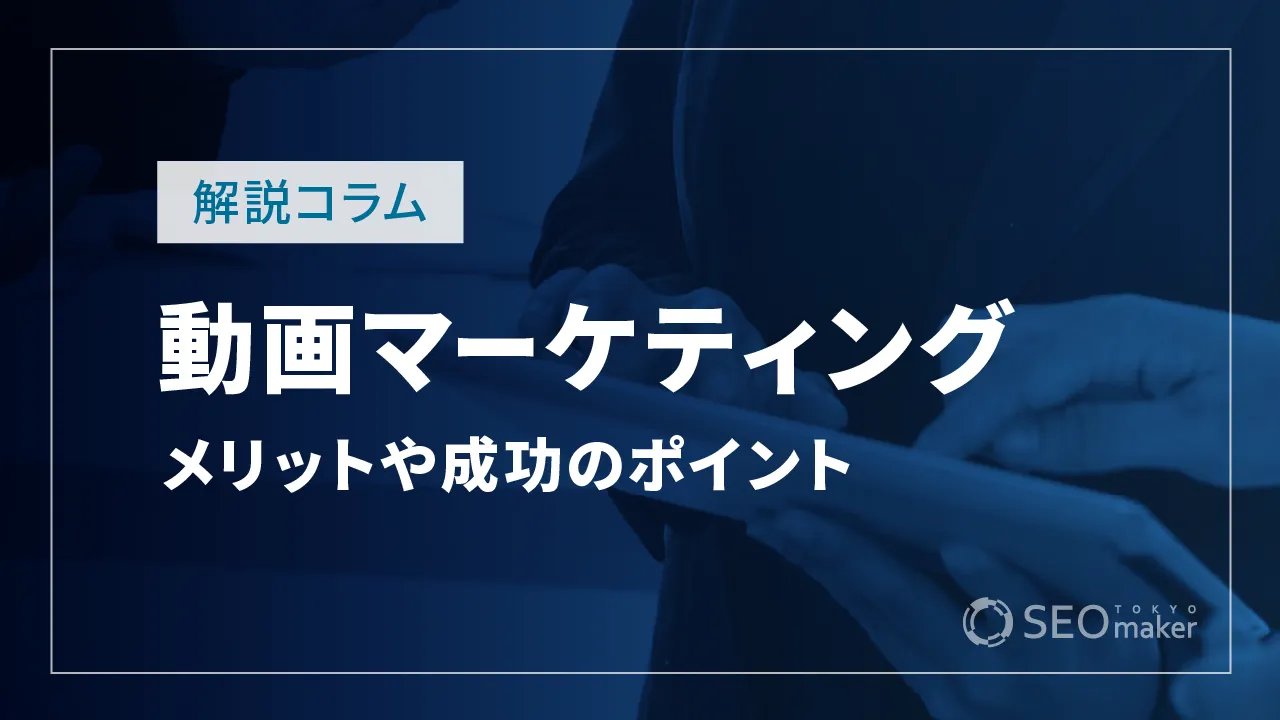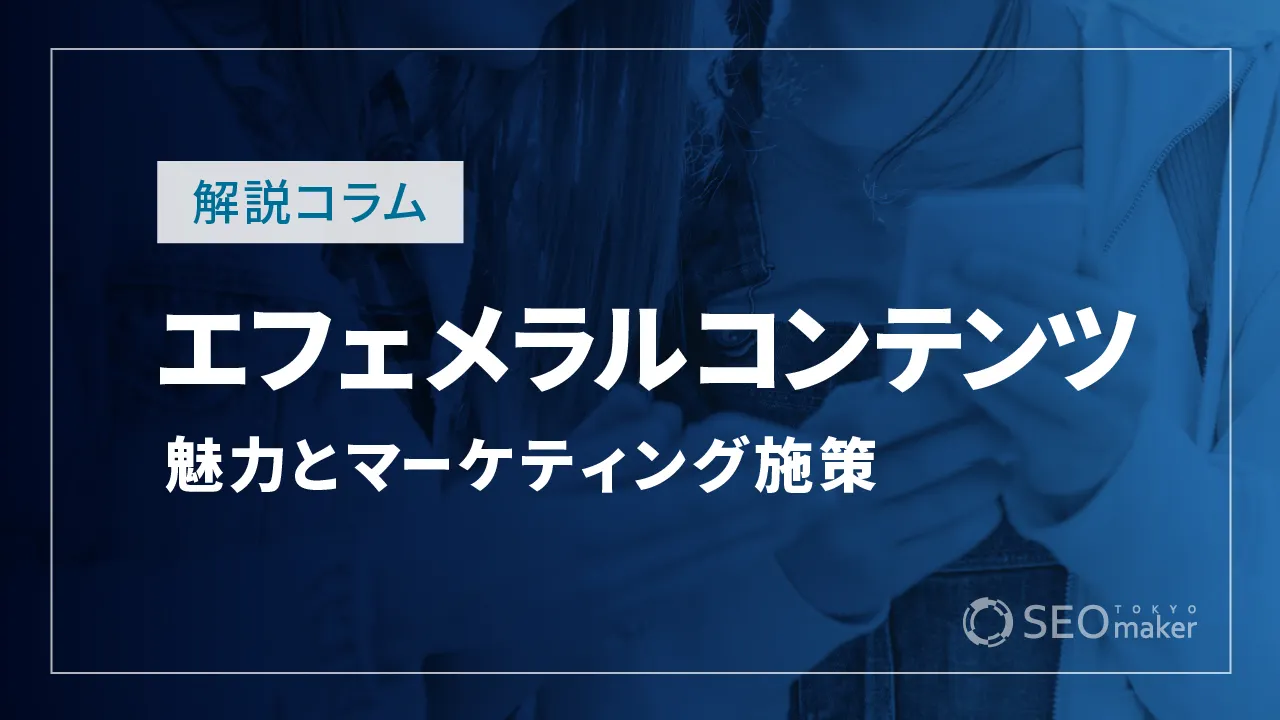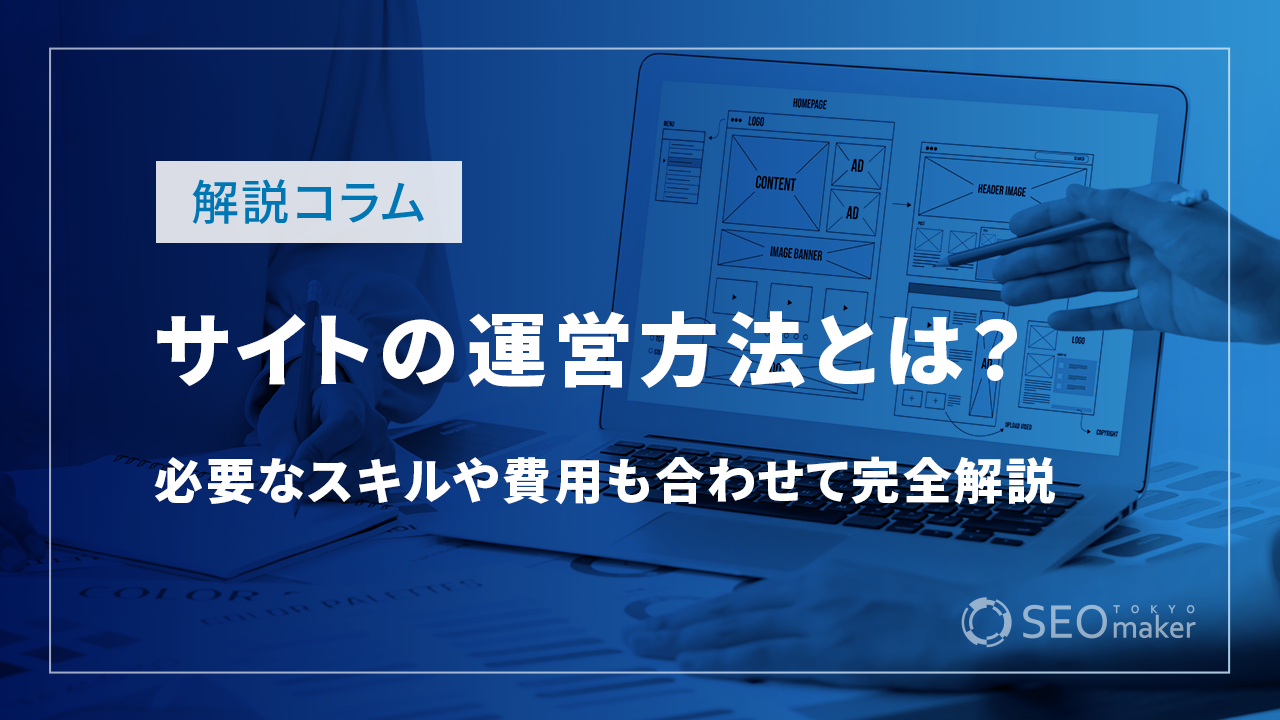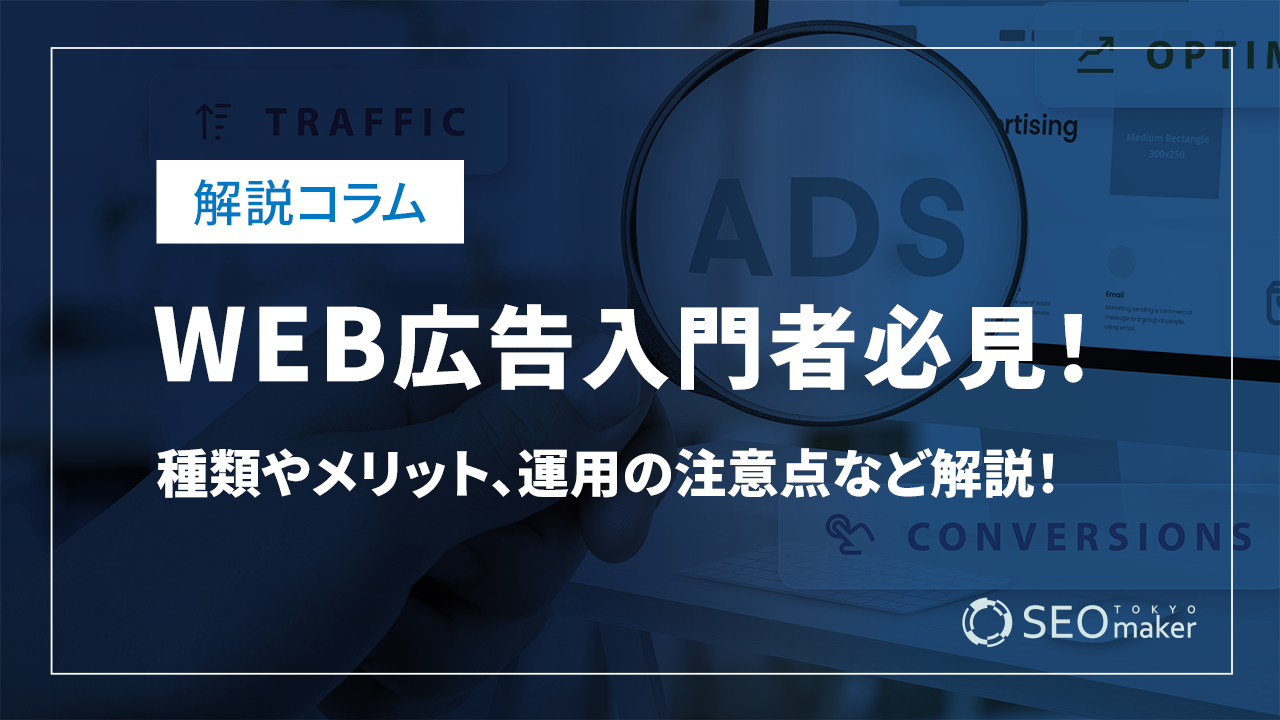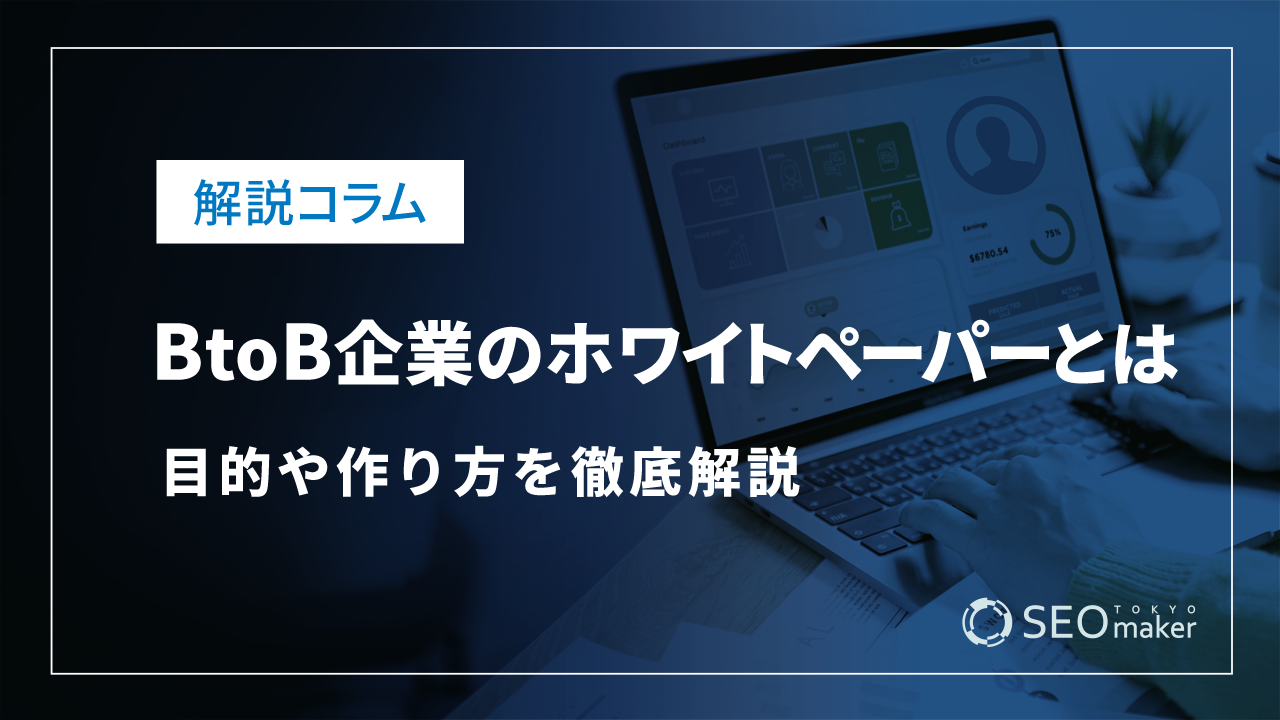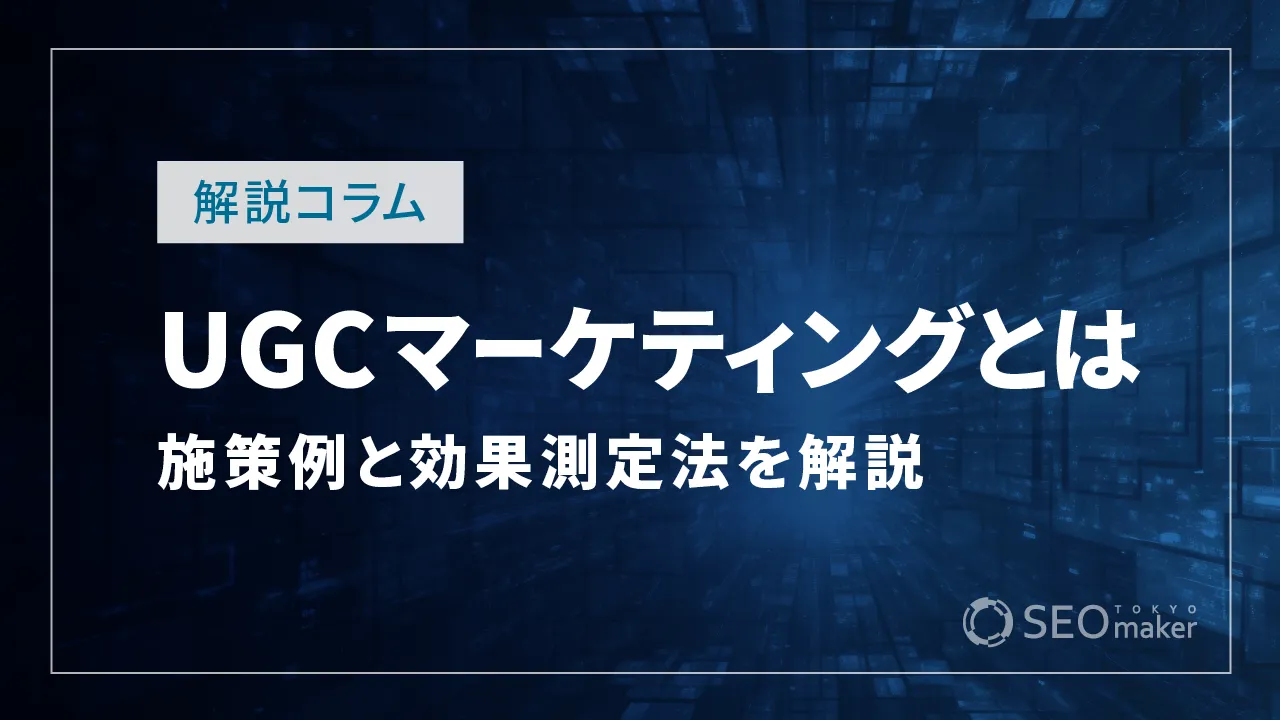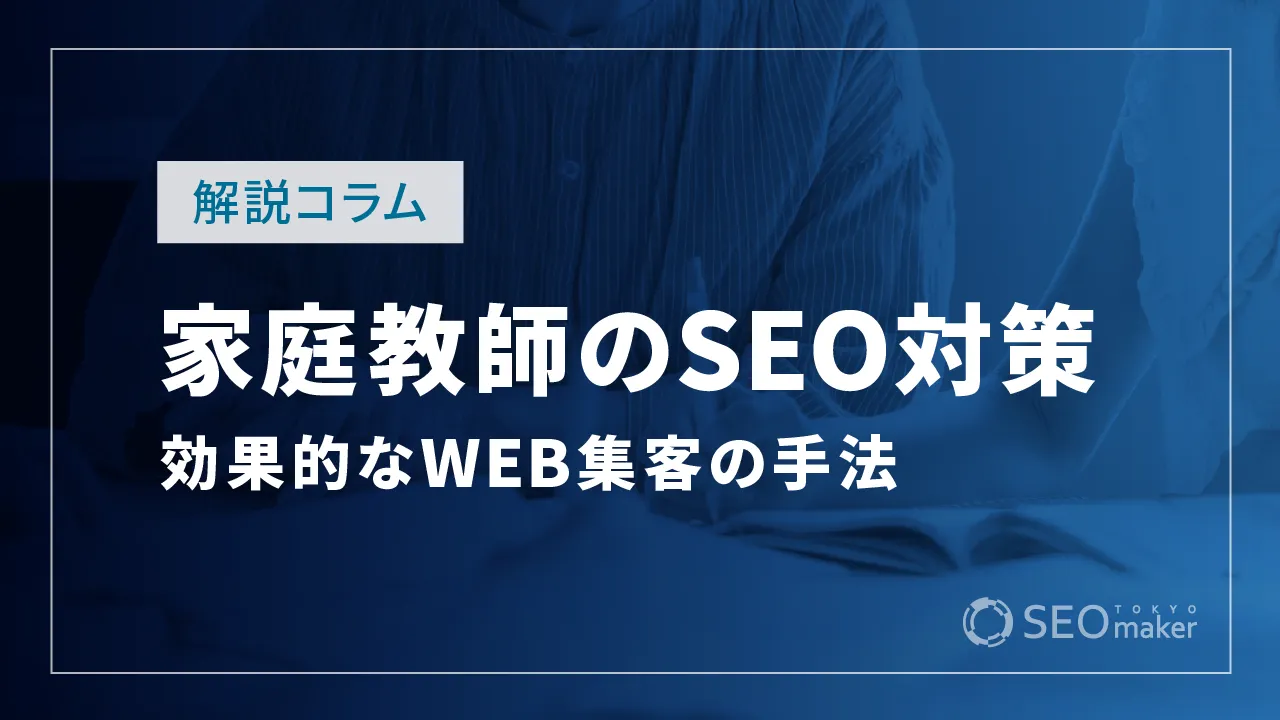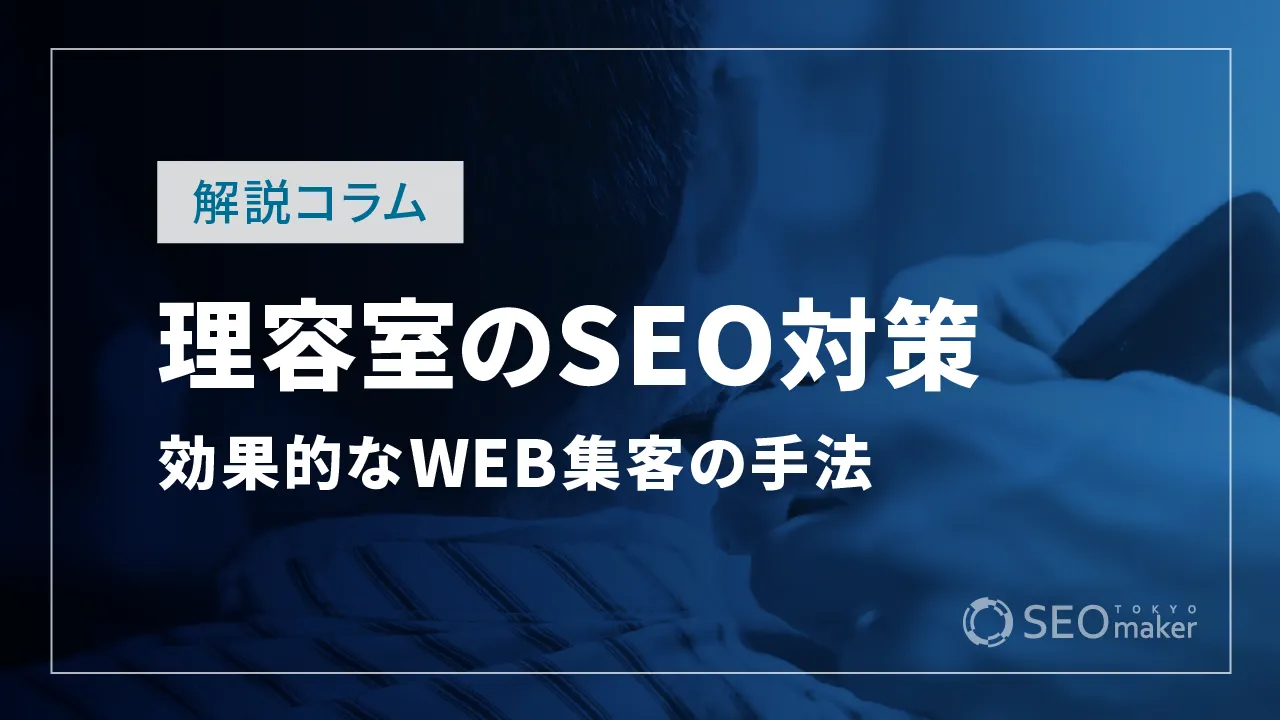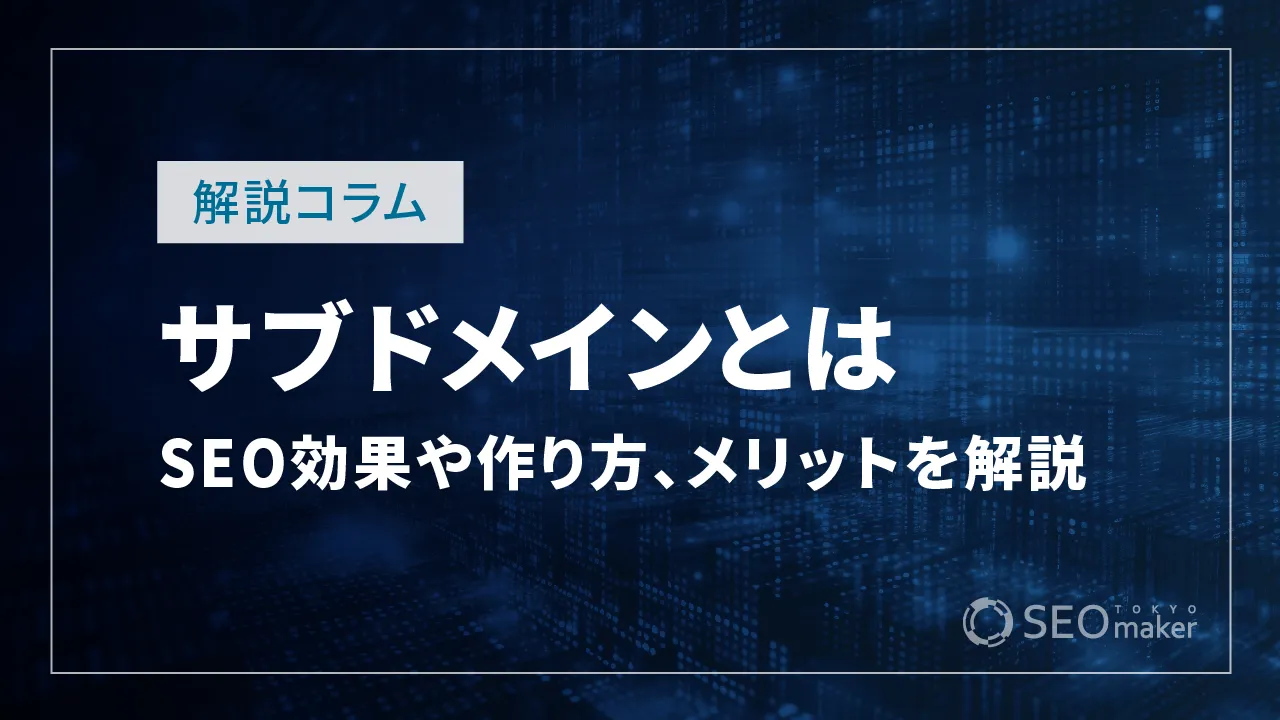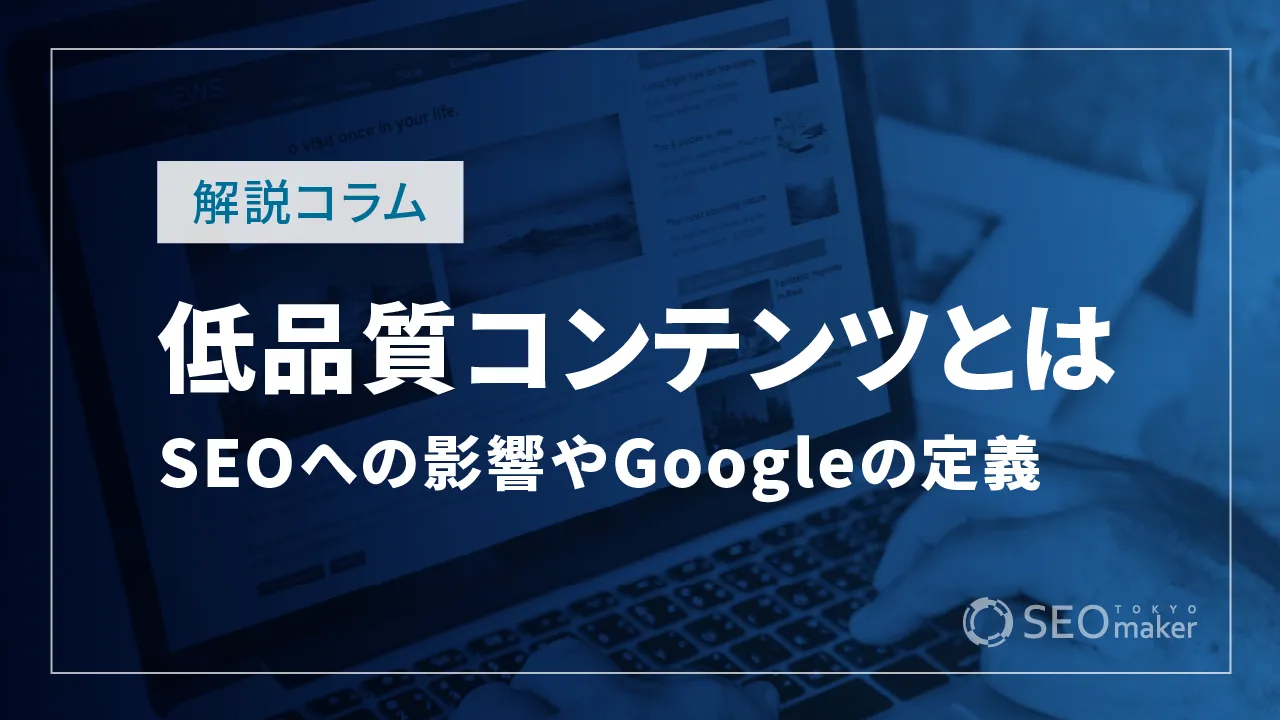ファンマーケティングとは?成功のポイントや手法と企業事例まで解説
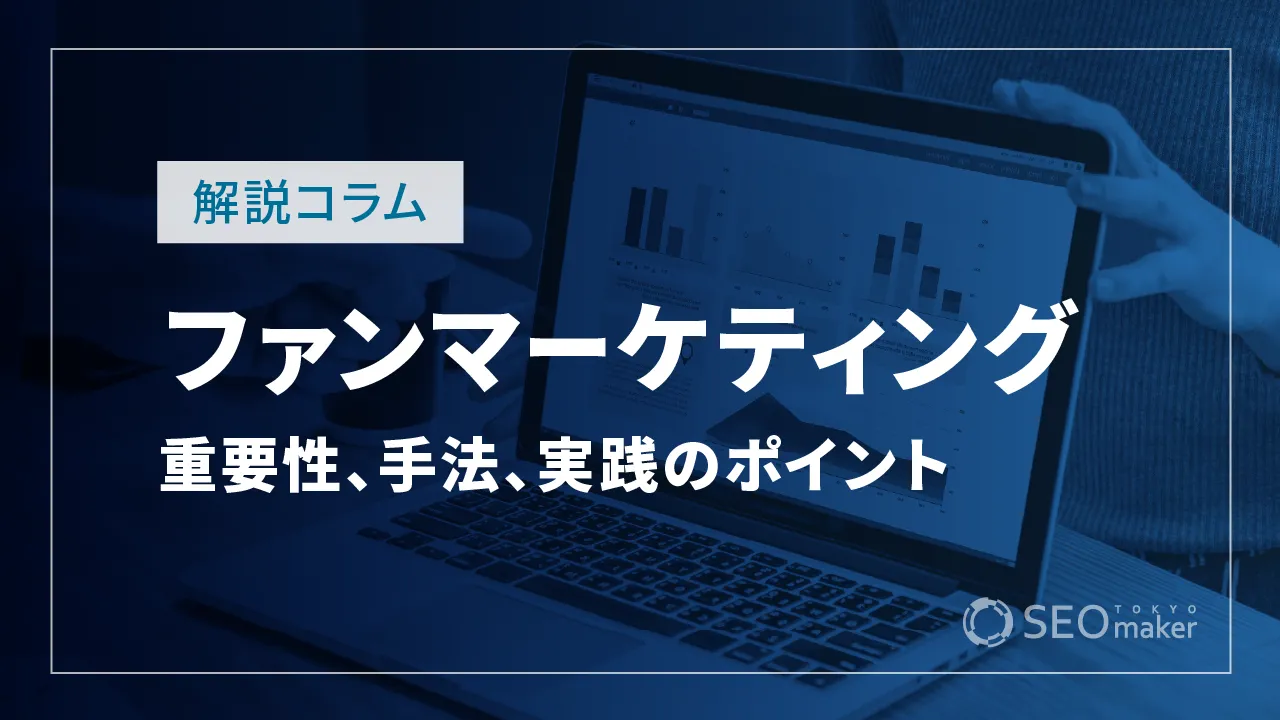
マーケティング手法を研究したことがある人なら、一度は「ファンマーケティング」という言葉を耳にしたことがあると思います。ファンマーケティングとは、企業やその商品・サービスに愛着を持つ「ファン(ロイヤルカスタマー)」を育成・活用し、継続的な購買や口コミによる拡散を促すマーケティング戦略です。
 この記事では、ファンマーケティングとは何か、その重要性や手法、成功のためのポイントなどを解説します。新たな顧客の獲得や、新しい視点やアイデアを求めている会社の担当者は、ぜひ参考にしてください。
この記事では、ファンマーケティングとは何か、その重要性や手法、成功のためのポイントなどを解説します。新たな顧客の獲得や、新しい視点やアイデアを求めている会社の担当者は、ぜひ参考にしてください。
ファンマーケティングとは
会社や商品、またはサービスを嗜好する人々(ファン)を育成し、そのような人々からのリピートビジネスを狙い、ロイヤリティを高めるマーケティング戦略を、ファンマーケティングと呼びます。また、ファンマーケティングのターゲットとなる顧客のことを、ロイヤルカスタマーと呼びます。これは、会社やその商品やサービスに対して愛着を持ち、継続的に購入や利用をしてくれる人を指します。
一方で、優良顧客という言葉もよく使われますが、こちらは商品やサービスを定期的に購入や利用するお客様を指します。また優良顧客は、競合や値段の変化によってそこから離れる可能性があるのに対し、ロイヤルカスタマーはそのサービスへの愛着によって、簡単な理由で離れることはないとされています。
なぜ今ファンマーケティングなのか
現在、多くの会社がなぜこの方法に注目するようになっているのでしょうか。
具体的な理由を3つの点で解説します。
新規顧客獲得が困難に
日本の人口が減少し、少子高齢化が進んでいることもあり、単身世帯が増えています。このような状況では、新しい顧客を獲得することが困難であり、会社側は、ターゲットの母数がそもそも少ないといった課題に直面しています。
さらに、現代社会は情報、商品、サービス、エンターテイメントが溢れており、情報過多の超成熟市場であると言えます。会社が「キャンペーン」や「値下げ」などを行っても、消費者に情報が届きにくく、心を掴むことが困難になっています。そのため、会社中心ではなく、消費者側の視点を取り入れた新しいマーケティング施策が必要であると考えられています。
LTVを重視する経営戦略への移行
新規顧客獲得が困難な状況下では、会社が既存顧客が商品やサービスを継続的に使い続けることを重視する傾向が強まっています。マーケティングに携わる人ならば、「パレートの法則」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。この法則によると、2割の重要顧客が8割の売上高を支えているということです。このことを考慮して、少数の重要顧客をリピーター化させ、LTVを高めることで、中長期的に効率的に収益を得られるという考え方を採るところが増加しています。
SNSの普及によるユーザーの情報発信能力や影響力の向上
SNSの普及によりユーザーの情報発信機会が増えた結果、ユーザー同士のコミュニケーションが盛んになりました。そのため、商品を初めて購入する際やツール導入の検討をする際には、多くの人が口コミサイトやSNSでの評判をチェックするでしょう。そのため会社は、ユーザーのメディアパワーを自社にプラスに活かす方法や、ユーザーの反応を考慮したブランディング戦略の策定などを考えることが重要になっています。その結果、既存顧客への強化アプローチを行い、クチコミやレビューを充実させようとする傾向が強まっています。
ファンマーケティングにおける主な手法
ここでは、主要な手法を6つ紹介します。
ファンミーティング
第1の手法は「ファンミーティング」です。この手法では、ヘビークライアントである顧客と会社とが直接的にコミュニケーションを取ることができます。ファンミーティングでは、商品やサービスに対する意見や要望などを顧客から聞くことができるほか、商品やサービスをより深く理解してもらったり、好感を持ってもらえる貴重な機会です。
最近では、コロナ禍により対面形式のファンミーティングが難しい状況にありますが、その代わりにオンライン上で実施するケースが増えており、遠方に住んでいる人でも参加が可能であるため、参加のハードルが低くなっています。
公式SNSアカウントを使ったファン育成
公式SNSアカウントを運用することで、ユーザーとのコミュニケーションを深めることができます。これにより、ユーザーは親近感を持ち、購買決定時に「あの会社だから買おう」と思うようになります。また、公式SNSアカウントの運用は初期投資が不要であり、広告予算が少ないなかでも手軽に行えるのが特徴です。
SNSキャンペーン
SNSキャンペーンは、SNS上で行うユーザー参加型の手法です。この手法では、ユーザーのアクションによってキャンペーンが拡散されます。例えば、リツイートやいいね、指定したハッシュタグを使った投稿などがあります。通常の広告では、会社が一方的にユーザーに向けて広告を配信するのに対し、SNSキャンペーンでは、ユーザーが受け取った情報を拡散することで、さらに他のユーザーにも伝わります。
このように、2次拡散が行われることで、広告配信ではカバーできなかったユーザーにもアプローチすることができます。
ライブ配信でのファンとの交流
ライブ配信を使った手法は、特定のプラットフォームやSNSで生放送のライブ配信を行い、会社やインフルエンサーなどがファンと交流することを指します。このようなライブ配信では、ユーザーが自分が推している人物などと「繋がれる場」であると感じ、積極的に参加します。最近では、ライブ配信中に商品を宣伝し、購買までのスキームを提供する「ライブコマース」という手法が注目されています。
クラウドファンディング
クラウドファンディングとは、インターネットを介して資金調達を行う手法のことです。これは、まだ発表されていない商品をユーザーに援助してもらう仕組みであり、早い段階で自社の熱狂的な応援者を獲得することが可能とされています。
また、クラウドファンディングを通じて支援してもらえることは、商品だけでなくプロジェクトの背景に賛同して応援してもらえることと同義です。これから発売する予定の商品やプロジェクトを提案する場合には、クラウドファンディングを検討することで、将来の自社のファンを見つけ出せるでしょう。
サンプリング体験
サンプリングとは、商品を提供し、製品をより理解してもらい、意欲を高めることで、リード顧客を獲得するためのSNSマーケティング手法です。
サンプリングは、SNSでの投稿を促すこともできます。そのため、ヘビークライアントの獲得に加え、商品やサービスに関するSNS投稿への露出が可能になります。サンプリングは、SNSキャンペーンと組み合わせることもできます。
また、一般的な消費者を対象としたモニターサイトに依頼して、サンプリングを実施することもあります。
ファンマーケティングのメリット・デメリット
肝心なメリットとデメリットについても解説します。
≪メリット≫
メリット①自然な拡散が期待できる
ファン自らがSNS等で製品を紹介してくれます。熱狂的なヘビークライアントは、自分が気に入ったサービスや商品を他の人にも知ってもらいたいという気持ちから、自然にそれをSNSや口コミを通じて宣伝してくれます。彼らの意見は説得力があり、非常に貴重な広報サポートとなります。
メリット②フィードバックが得やすい
ユーザーからのリアルな意見が獲得がしやすくなります。ファンマーケティングでは、顧客が会社や商品、サービスを改善してほしいと考え、自発的に情報を提供する傾向があります。これにより彼らからのフィードバックを安価で獲得でき、また彼らは、自分が参加できることで自信を持つことができます。このように、両者にとってメリットが生まれるのです。
メリット③安定収益につながる
顧客の中には、全体の売上の80%を作る20%が存在すると言われています。そのため、良質なファンを育成することで、安定した売り上げを確保し得ると言われています。
また近年、生涯的な価値(LTV)が注目されています。LTVは、顧客から生涯にわたって得られる利益を意味します。LTVを最大化することで、安定した売上を得ることができるとされています。
≪デメリット≫
デメリット①成果に時間がかかる
ファンマーケティングで得られる成果は、その方法を続けていくことで得ることができます。しかし、そのためには長い期間を要します。また顧客を続けて獲得することは容易ではありません。そのため、成果が出るまでには長い時間を要することがあるので注意が必要です。
デメリット②成長停滞のリスク
ファンマーケティングを重視することで、会社の成長意欲が弱まることがあります。成功すると、売上が安定するため、成長を目指すよりも現状の維持に力を注ぐ傾向になるかもしれません。このようになると、競合他社に差をつけるための行動を起こさず、お客目線から離れるリスクもあります。そのため、常に成長を意識した活動を行うことが重要です。
ファンマーケティングの注意点
ファンマーケティングを成功させるには、施策を実行するだけでなく、運用面でもいくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
まず基本となるのは、商品やサービス自体の質です。どれだけ魅力的な施策を行っても、提供価値が低ければファンの信頼を得ることはできません。
次に、ファンのSNS投稿や口コミを日常的にモニタリングし、適切に対応する姿勢も欠かせません。好意的な発信には感謝を示し、批判的な声には真摯に対応することで、信頼関係を深めることができます。
さらに、ファンの関心やニーズを把握し、それに沿ったコンテンツや体験を提供することも重要です。顧客目線で企画を進めることで、エンゲージメントの向上が期待できます。
ファンとの関係が深まるほど、企業への期待も大きくなります。過度な期待を生まないよう、できること・できないことを明確にし、誠実な姿勢で向き合うことが大切です。
そして、関係を一過性に終わらせないためには、継続的に関われる仕組みを整えることが求められます。定期イベントや会員限定コンテンツなど、ファンが参加し続けられる場を設けることで、長期的な関係性を築くことができます。
ファンマーケティング成功のためのポイント
以下より、施策を進めるにあたってのポイントを5点紹介します。
ファンの定義を決める
まずは、自社のファンがどのような人物であるかを明確にすることが重要です。一般的には、「ファン=高い購買金額を支払う顧客」と考えられがちですが、単純な金額での顧客評価には限界があります。他社の商品に気に入っていないなどの理由で、自社の商品を購入することを余儀なくされることもあります。
そのため、ファンの定義の際には、売上に加え顧客ロイヤリティも確認することを心がけましょう。SNSで自社商品について肯定的に言及したことがある人や、前向きな商品レビューを書きこんだことのある人は、潜在的なロイヤルカスタマーの可能性があります。金額だけでなく、顧客ロイヤリティも十分に考慮することが重要です。
顧客接点と購入までの導線整理をする
商品やサービスを利用することだけでなく、SNSやその他の媒体での情報発信を通じてお客さんとの接点を増やすことが大切です。
彼らが自社のファンになる可能性は、購買金額だけでなく、SNSでの肯定的な発言やレビュー、および顧客ロイヤリティを考慮することで増やすことができます。また、自社の主要メディアにアクセスする機会を増やすことで、会社やブランドについてより深く理解してもらうことができます。
一方通行ではなく双方向のやり取りにする
会社から顧客に向けた情報発信だけではなく、彼らとのやり取りを活発にすることを大切にしましょう。SNSで自社を検索した際に出てくる記事や、ブランドや商品に関する投稿に対して「いいね」を押すようにしたり、肯定的な投稿に対してお礼の返信をすることで、より密なコミュニケーションを保つことができます。
こうしたやり取りが、他社との差別化につながり、ヘビークライアントを形成するのです。
ファン同士のコミュニケーションも逃さない
ファン同士が交流するようなコミュニティの場も重要です。そのような場を作るにあたって、会社側は、好奇心を持たせるテーマを設定したり、発言を促すようなインセンティブを与えることで、コミュニティ内でのやりとりを促すことができます。
また、ファン同士が初めて会ってもすぐに打ち解けることは難しいので、会社側はそのような場をサポートすることで、より良いコミュニケーションを促すことができます。
需要のポイントを把握する
ニーズを積極的に取り入れることも欠かせません。具体的には、商品やサービスに対する満足度調査や、新商品のモニター募集などを行い、お客様のフィードバックを取り入れることで、商品やサービスの改善や、「お客様の声から誕生した商品」の開発を行うことができます。
また、ニーズを把握することで、同じようなニーズを持つ潜在顧客に対する訴求もより効果的になるでしょう。
ファンマーケティングの主な成功事例
最後に、いくつかの成功事例について見ていきましょう。
松屋フーズ
牛丼チェーン「松屋フーズ」は、Instagramを使ったファンマーケティングを通じて成功を収めました。牛丼は、一般的には「男性が多く利用する」「ファストフード」というイメージがありますが、同社のInstagramアカウンントでは、若者にも親しみやすい「サブカルチャー」の要素を含んだ投稿を行っており、若者を中心に人気を得ています。
JA全農
JA全農のTwitterアカウントでは、ユーザーに有用な食品レシピや、食材の知識を発信することで、多くの支持を得ています。JAは農業者との関わりが深く、旬の野菜や食材の知識など、自社ならではの強みをわかりやすく発信しており、エンゲージメントも高く、コアなヘビークライアントを獲得しています。
岩塚製薬
岩塚製菓のInstagramアカウントでは、お煎餅を主軸にした投稿を中心に行っており、それに対してフォロワーからのコメントには公式アカウントが丁寧に返信していることで、親密なコミュニケーションを構築しています。これにより、ファンとの関係値を高めることに成功しています。
まとめ
 ここまでファンマーケティングについて解説してきました。ファンマーケティングは、新規顧客の獲得が難しくなっている今、顧客との信頼関係を深め、長期的な収益を生み出す重要なマーケティング手法です。ロイヤルカスタマーの育成を通じてLTVを高め、口コミやSNSによる自然な拡散を促すことで、効率的かつ持続的なブランド成長を実現できます。そのためには、質の高い商品・サービスの提供、SNS上での双方向コミュニケーション、そしてファンが継続的に関われる場の設計など、運用面でも丁寧な戦略が求められます。短期的な成果にとらわれず、顧客との関係性を育てる長期的な視点こそが、ファンマーケティング成功の鍵です。企業の価値を理解し、応援してくれる「本当のファン」とのつながりを築いていきましょう。
ここまでファンマーケティングについて解説してきました。ファンマーケティングは、新規顧客の獲得が難しくなっている今、顧客との信頼関係を深め、長期的な収益を生み出す重要なマーケティング手法です。ロイヤルカスタマーの育成を通じてLTVを高め、口コミやSNSによる自然な拡散を促すことで、効率的かつ持続的なブランド成長を実現できます。そのためには、質の高い商品・サービスの提供、SNS上での双方向コミュニケーション、そしてファンが継続的に関われる場の設計など、運用面でも丁寧な戦略が求められます。短期的な成果にとらわれず、顧客との関係性を育てる長期的な視点こそが、ファンマーケティング成功の鍵です。企業の価値を理解し、応援してくれる「本当のファン」とのつながりを築いていきましょう。