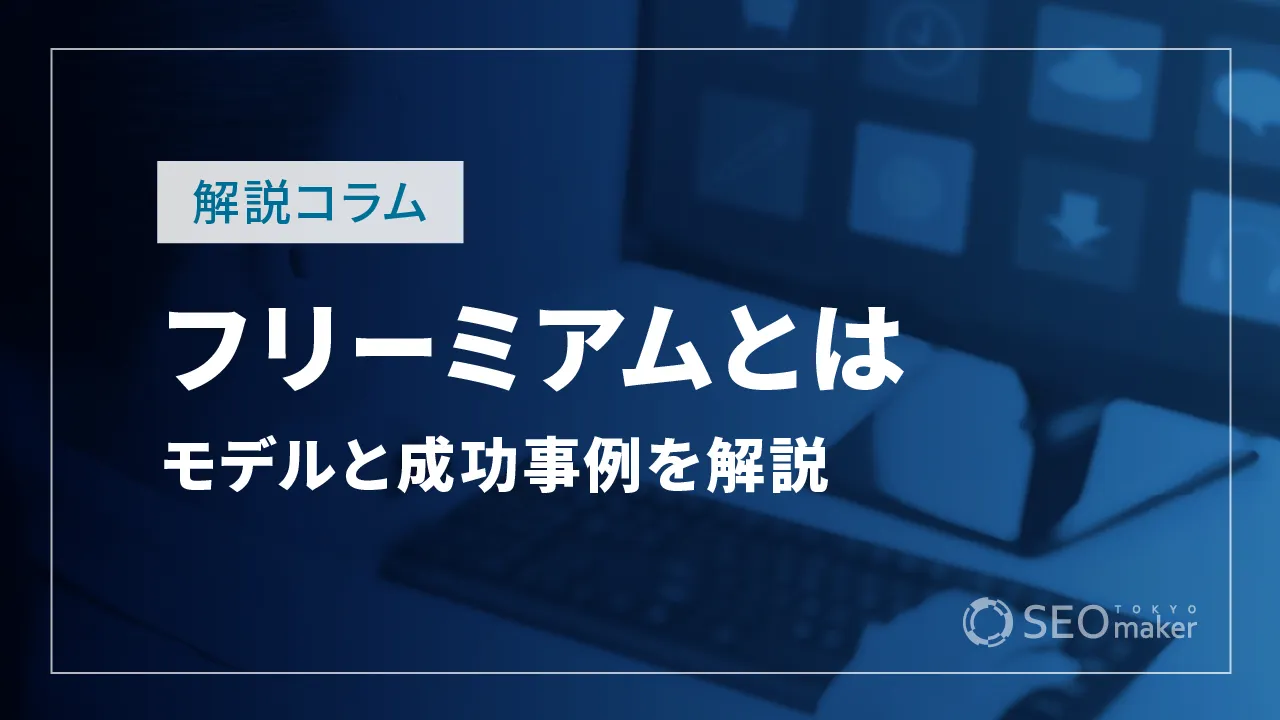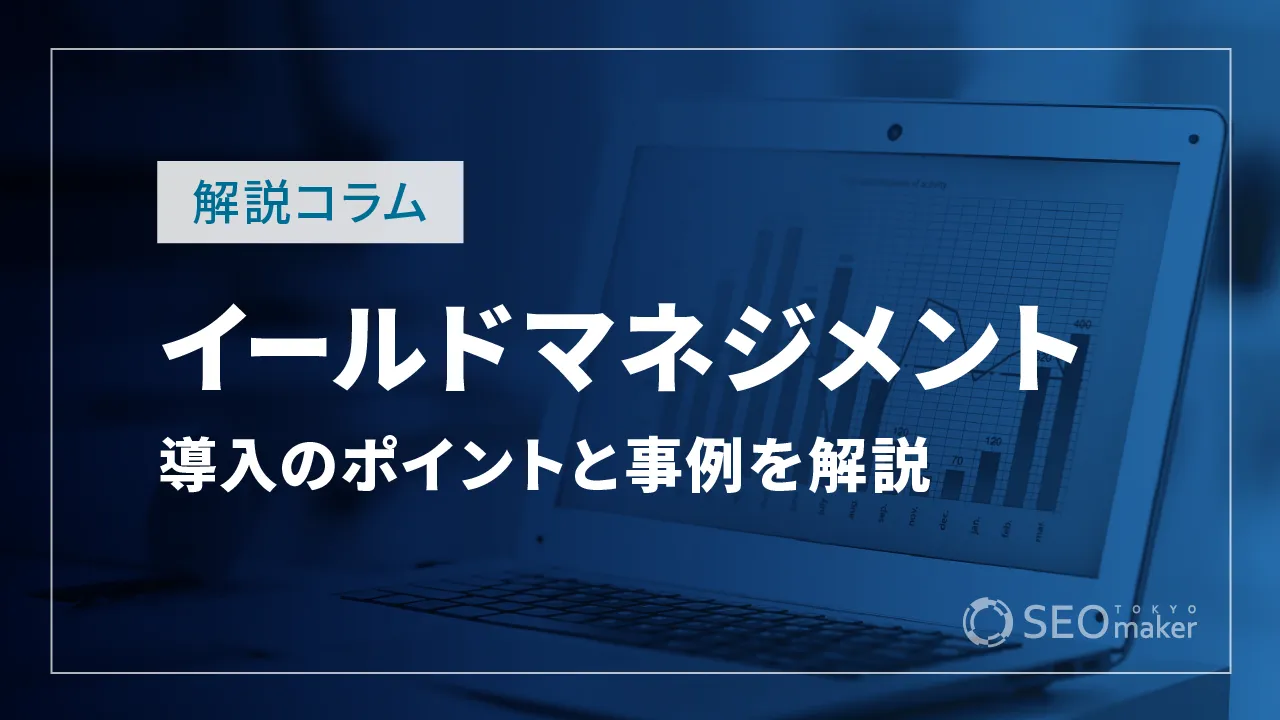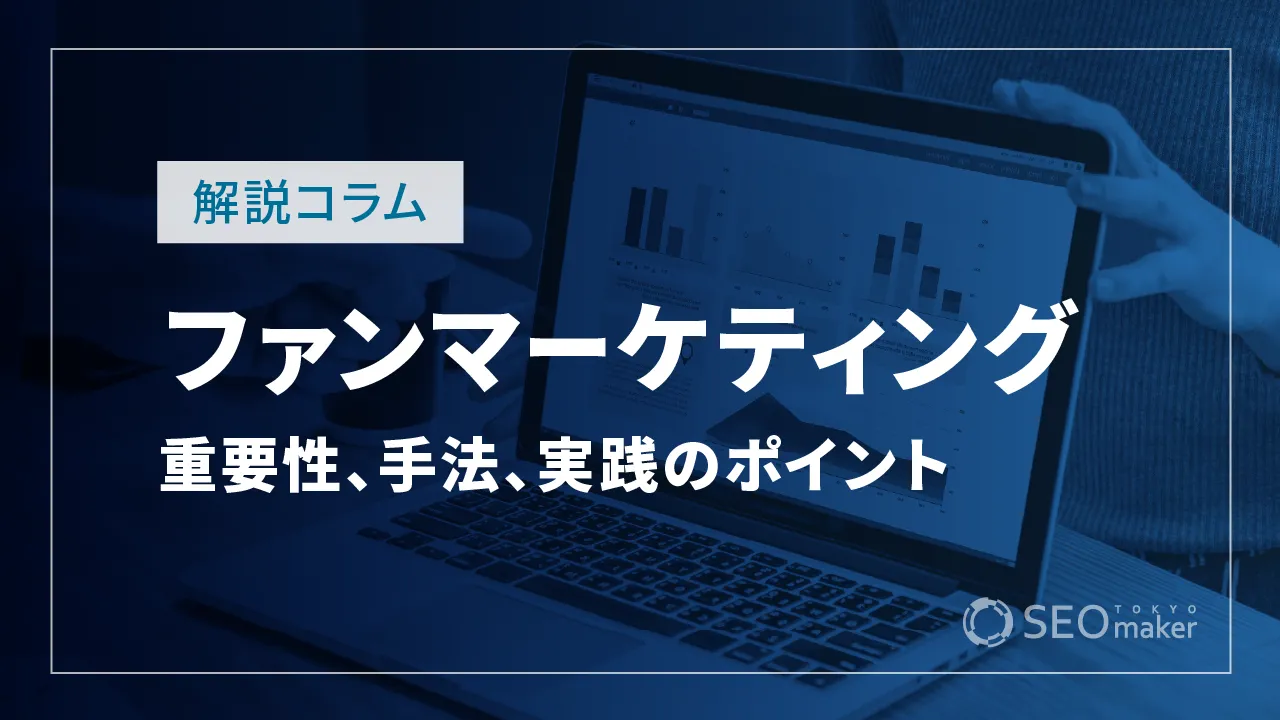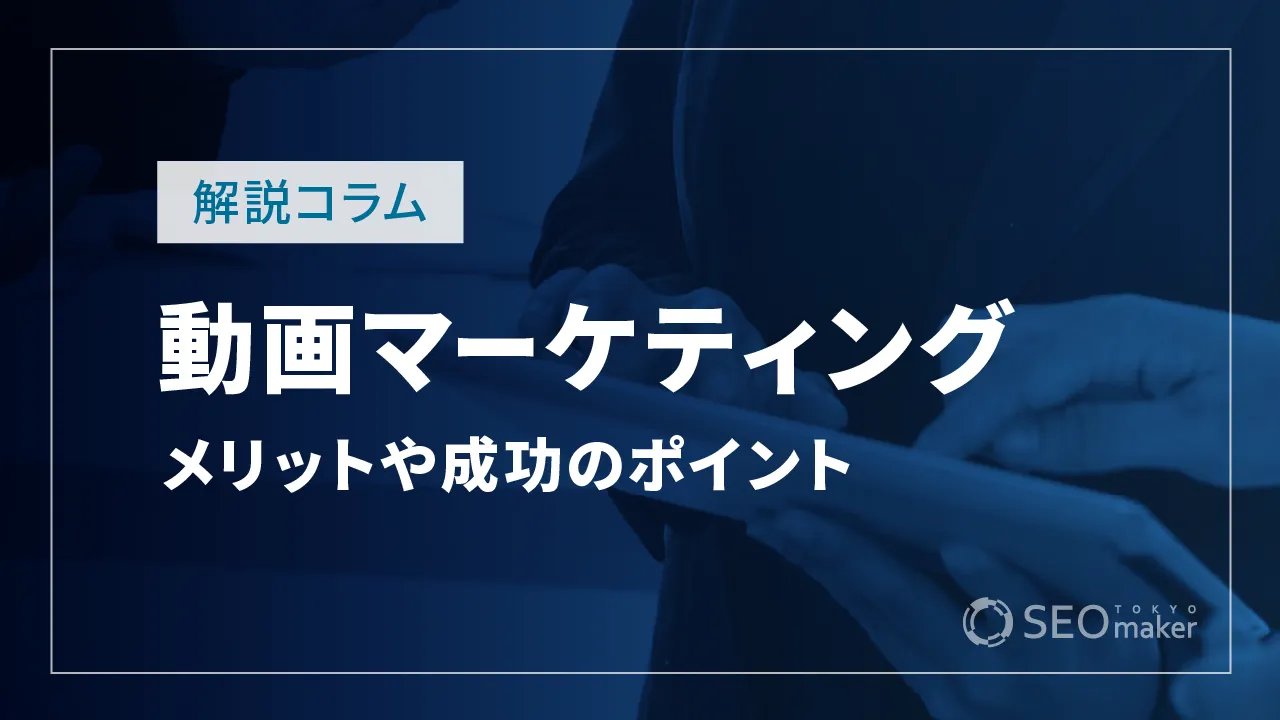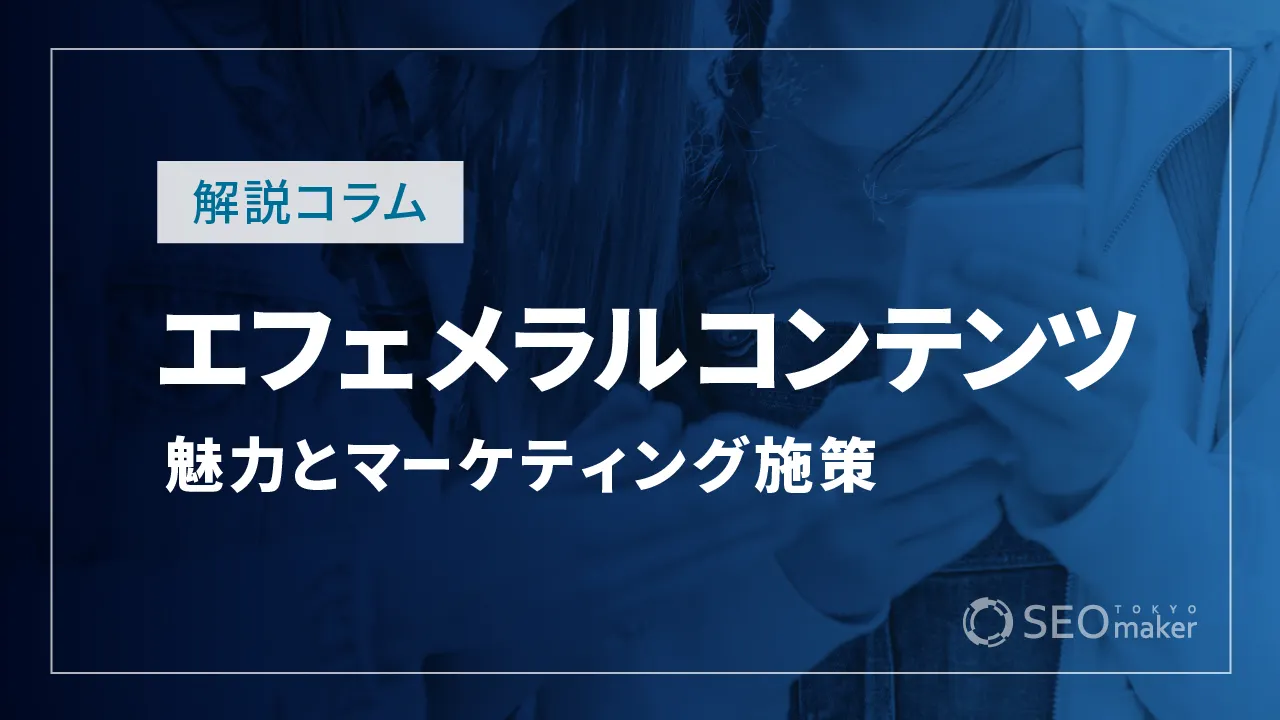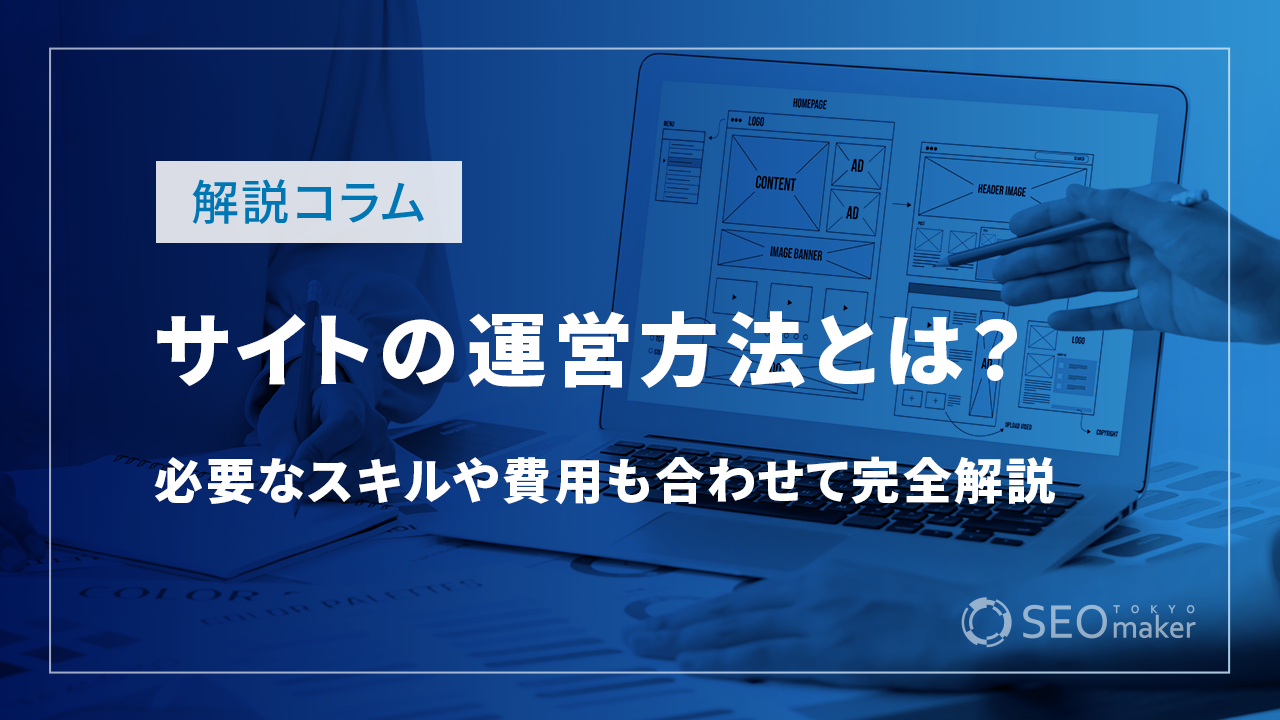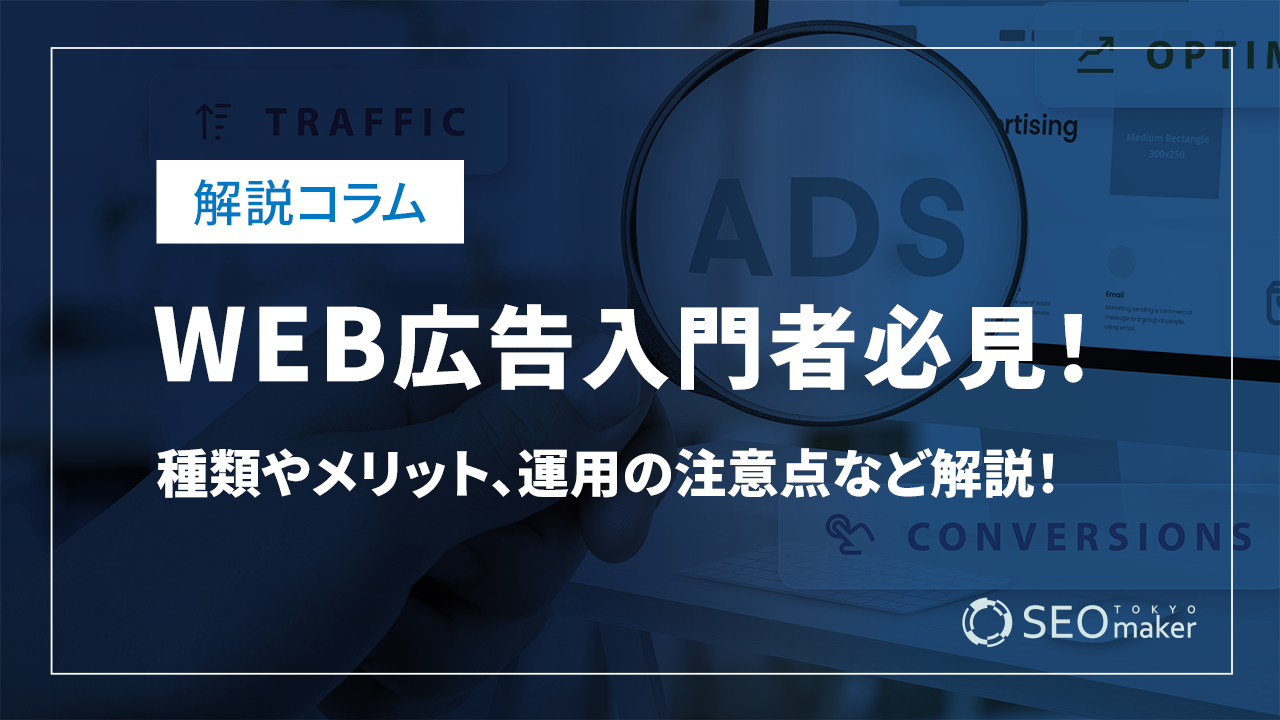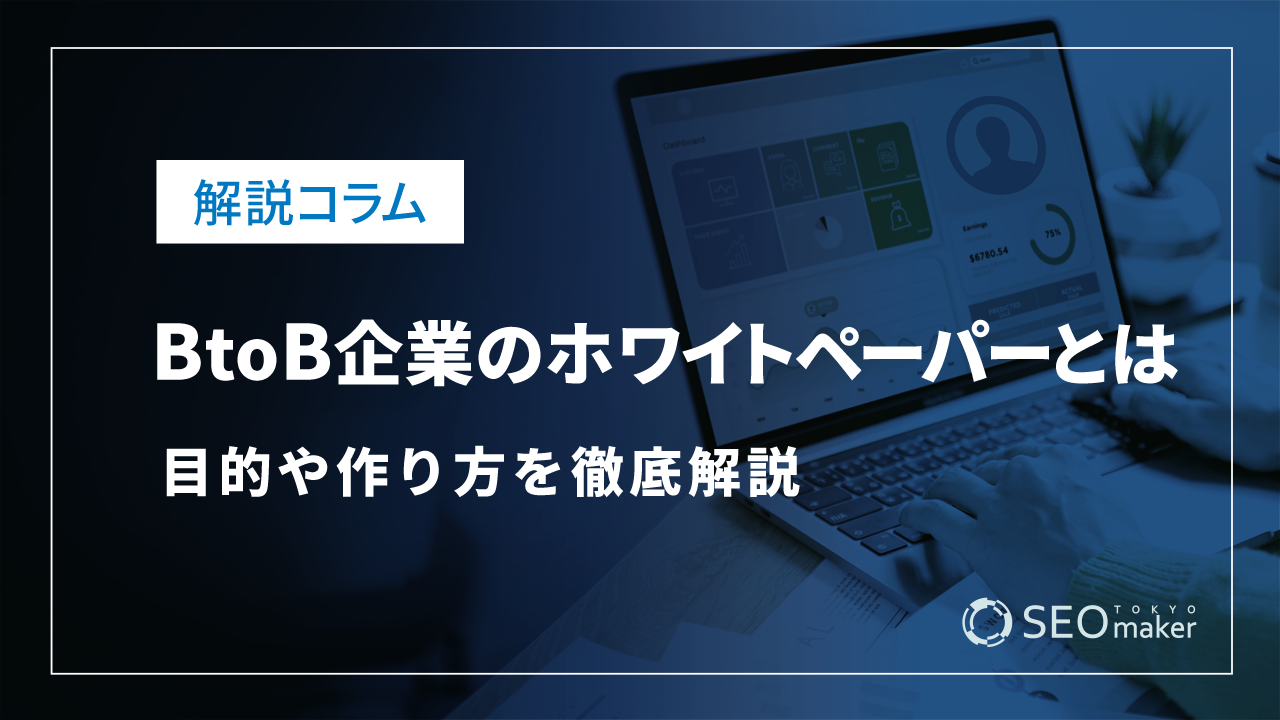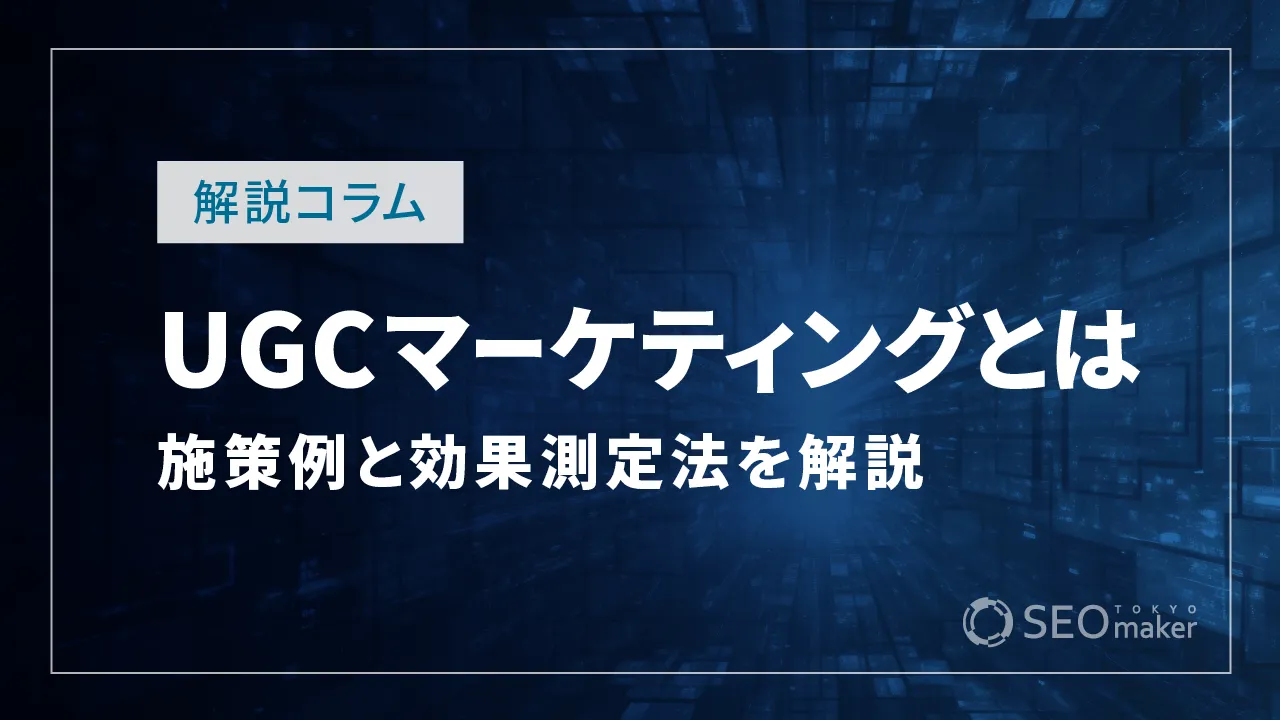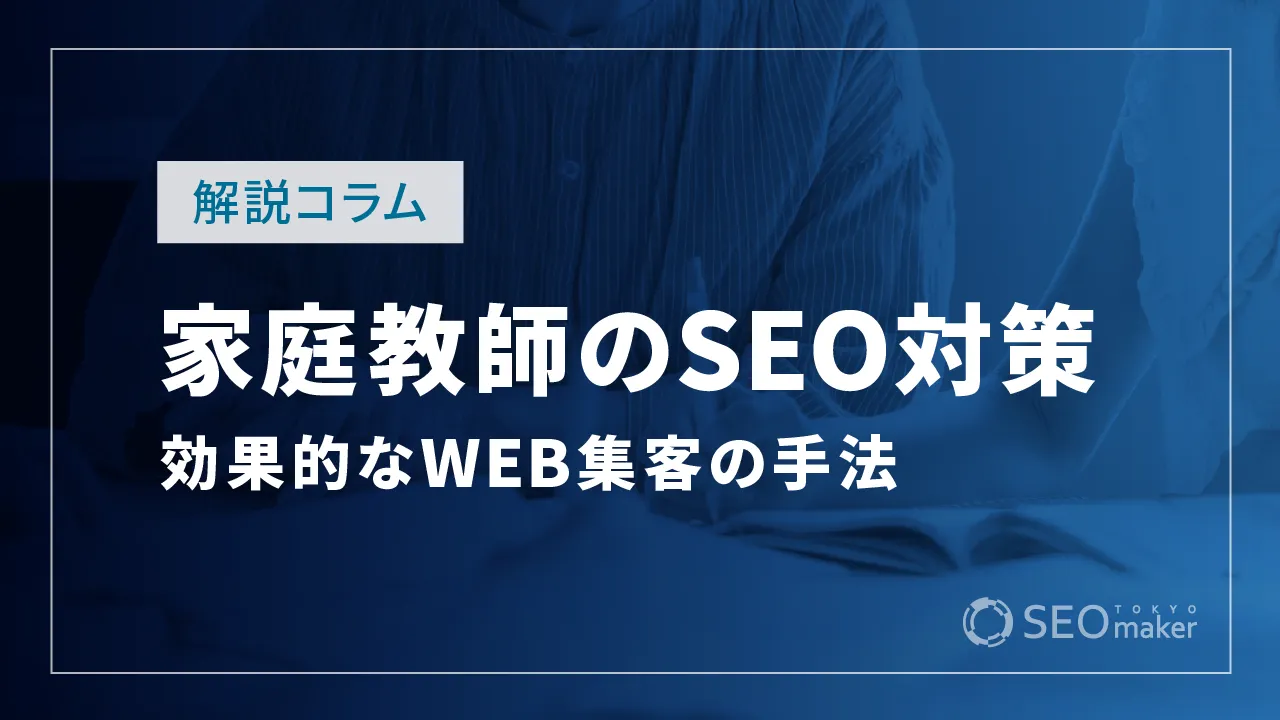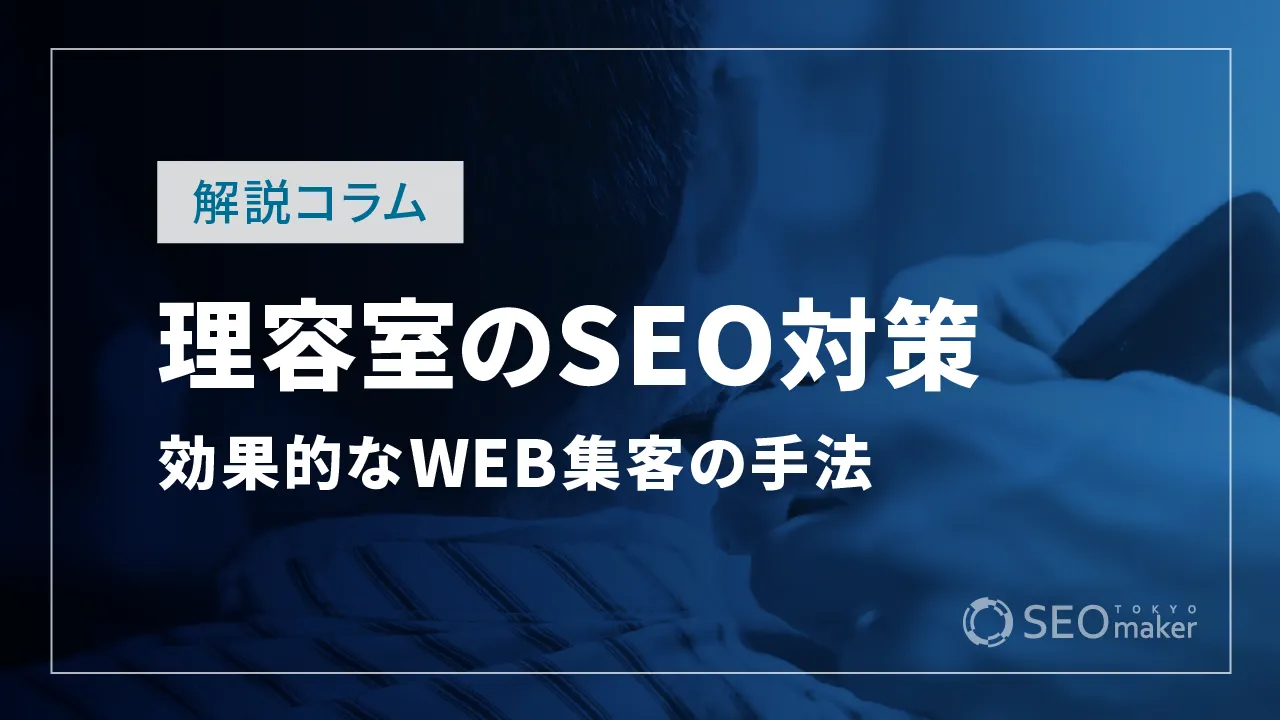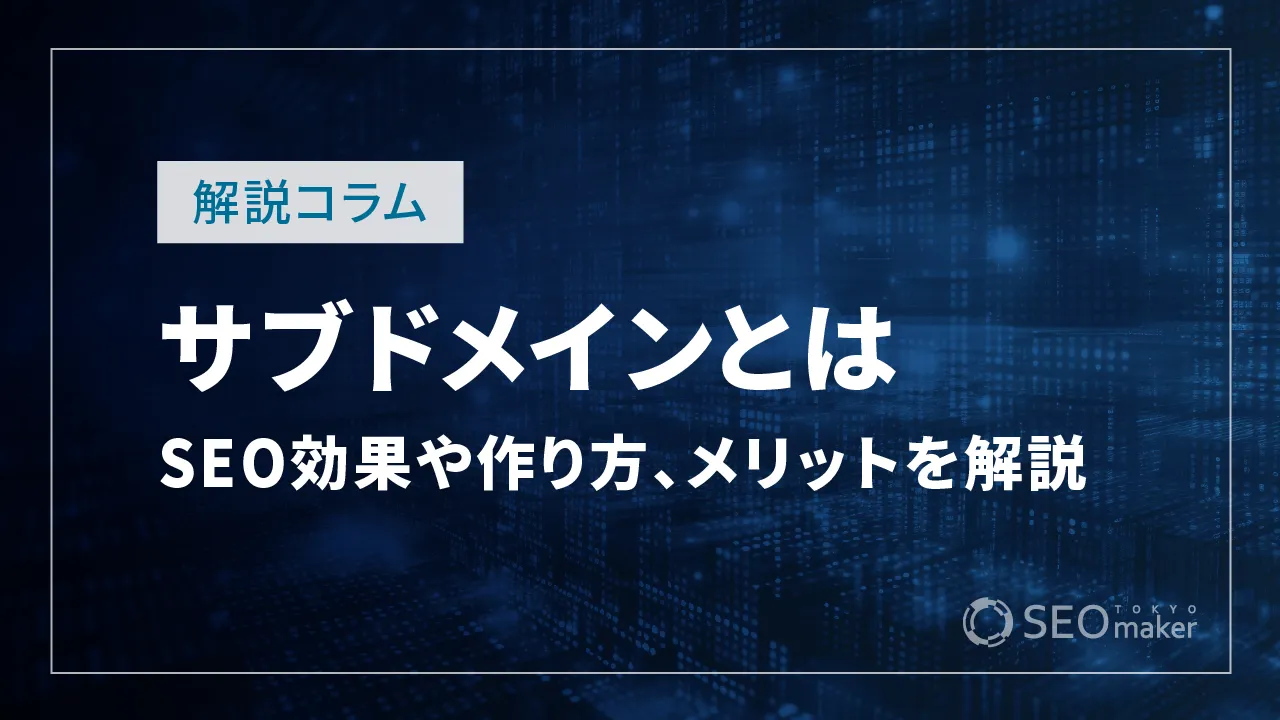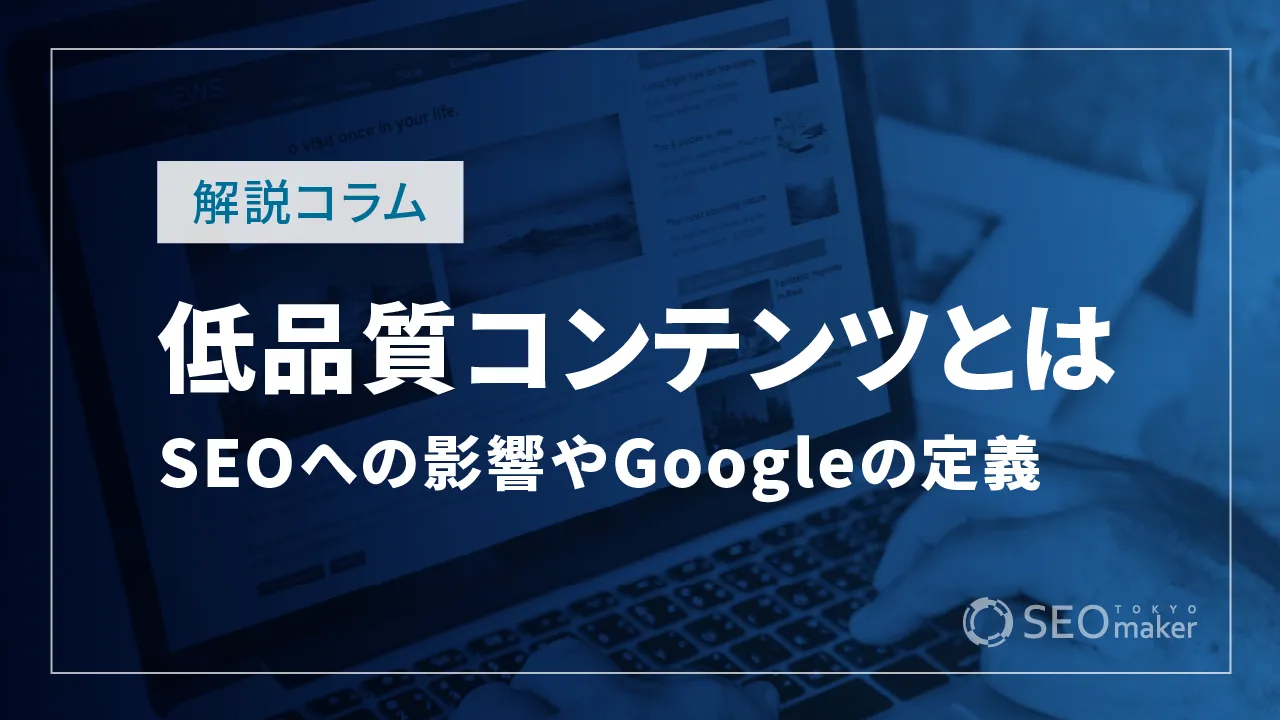フライホイールとは?導入効果と実施する際のポイントをわかりやすく解説
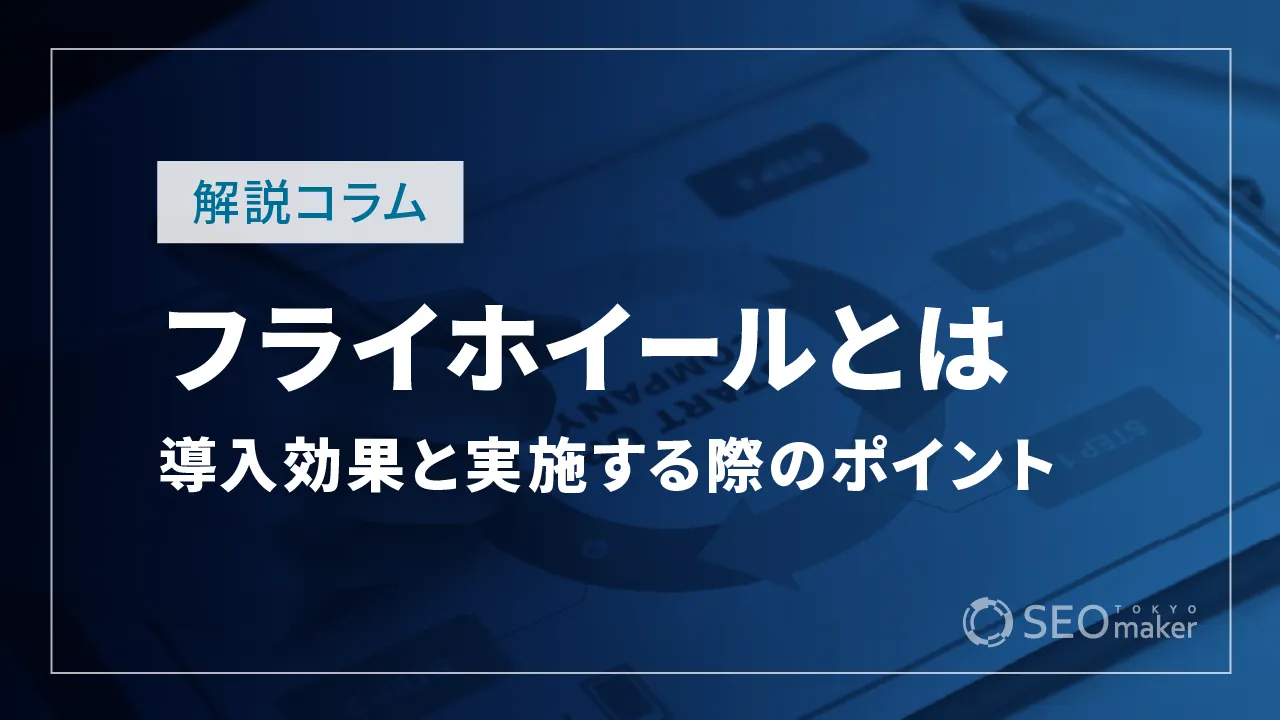
フライホイールモデルは、近年マーケティング業界で多くの注目を集めています。フライホイール(Flywheel)とは、顧客体験をビジネスの中心に据え、持続的な成長を実現するマーケティングモデルです。ただし自社でもフライホイールモデルの導入を検討しているものの、正しく理解できていない担当者も少なくありません。
 そこで今回は、フライホイールモデルの概要や導入効果、実施する際のポイントを解説します。フライホイールモデルで成功した事例も紹介するため、実際に導入を進める際に活かしましょう。
そこで今回は、フライホイールモデルの概要や導入効果、実施する際のポイントを解説します。フライホイールモデルで成功した事例も紹介するため、実際に導入を進める際に活かしましょう。
フライホイールとは
米国のマーケティングソフトウェア会社であるHubSpot社によって提唱された概念で、顧客体験をビジネスの中心に据え、持続的な成長を実現するマーケティングモデルです。本来フライホイールは電車や自動車の車輪に使われる部品で、回転の速度が速くなるほど生み出すエネルギーが増すといった機械構造であることが特徴です。
このようなフライホイールの構造を参考に、ビジネスに落とし込んだモデルがフライホイールになります。営業やマーケティングなど各部署が協力して顧客の興味を惹き、信頼関係を築いて顧客の満足度を高める図式です。満足度の高い顧客は新規顧客を連れてきてくれるため、ビジネスを成長できます。
ファネルとの違い
従来のビジネスモデルであるファネル型では、マーケティング、営業、カスタマーサポートといった部門が、顧客を順番にバトンリレーのように引き渡していきます。プロセス自体はシンプルで効率的に見えますが、顧客体験を重視していないため、期待した成果を得られないケースも多くありました。
近年はインターネットやSNSの普及により、紹介や口コミが購買行動に与える影響が非常に大きくなっています。この変化により、従来型のファネルでは新規顧客を獲得できても、そこから新たな顧客を生み出す流れを作ることが難しくなりました。
一方、フライホイールモデルでは、既存顧客の満足度を高めることで、その顧客自身が新たな顧客を呼び込んでくれる仕組みを作り出します。単なる一方通行のプロセスではなく、顧客を中心に据えた成長サイクルを生み出せる点が大きな違いです。
フライホイールの仕組み
ビジネスにおけるフライホイールは、車輪と同じように回転速度・摩擦・サイズという3つの要素によって成長力が左右されます。
この3つのポイントを意識することで、より強力にフライホイールを回し、ビジネスを加速させることができます。
ここでは、それぞれの要素について詳しく見ていきましょう。
回転速度
フライホイールの回転速度を上げるには、ビジネスに強い推進力を与える施策を加える必要があります。
具体的には、インバウンドマーケティング、フリーミアムモデル、販売プロセスの最適化、有料広告、リファラルプログラム(紹介制度)などが挙げられます。
これらの施策を通じて、顧客に質の高い体験を提供することが、フライホイールのスピードアップには欠かせません。
摩擦を減らす
回転を妨げる「摩擦」は、フライホイールのエネルギーを低下させる大きな原因になります。
摩擦を生む要素には、非効率な業務プロセス、コミュニケーション不足、顧客ニーズとのズレなどが含まれます。
これらを防ぐためには、チーム体制の見直しやカスタマーサポートの改善、顧客満足度向上の取り組みが重要です。
摩擦を最小限にすることで、フライホイールはよりスムーズに、力強く回り続けます。
サイズを大きくする
回転速度が上がり、摩擦が減ったとしても、フライホイール自体の「サイズ」が小さいと大きな成長は見込めません。
ここで言うサイズとは、顧客の目標達成をどれだけ強力にサポートできるかを指します。
カスタマーサービスの充実、マルチチャネルでのサポート体制、導入支援、ロイヤルティプログラムの提供などを通じて、顧客の成功体験を後押しすることが重要です。
これにより、より多くの顧客があなたのブランドを推奨してくれるようになり、さらに大きな成長エネルギーを得ることができます。
フライホイールの導入効果
従来のビジネスモデルに慣れている企業が、まったく異なるフライホイールを導入して担当者に負担がかからないか不安に感じる人もいるはずです。ただしフライホイールの導入により多くの効果を得られます。主な導入効果は、次のとおりです。
- 見込み客をうまく活用できる
- 柔軟な企業体制を構築できる
- 顧客との関係性を維持できる
見込み客をうまく活用できる
ビジネスを成長させるには、見込み客をいかに既存顧客にするかが重要なポイントになります。ただ商品やサービスが溢れる現代において、一方的に企業が情報発信したりアプローチしたりしても見込み客を獲得するのは難しいです。
フライホイールは、既存顧客が新規顧客に購買を促す循環モデルです。企業が情報発信するより、友達や第三者の評判や口コミが見込み客の購買決定に大きく影響します。見込み客の獲得が課題になっている場合は、フライホイールモデルが最適です。
柔軟な企業体制を構築できる
フライホイールを導入すれば、柔軟な企業体制を構築できる効果を得られます。一般的な企業では、営業やマーケティングなど各部署が分断されているのが現状です。これでは各部署で軋轢が生まれて、顧客との関係性にも悪影響を及ぼすことがあります。
このような問題を解決するには、柔軟に対応できる組織づくりが欠かせません。フライホイールは、各部署をまとめて一貫したサポートを提供することが可能です。顧客に十分なサービスを提供できるため、顧客満足度の向上につなげられます。
顧客との関係性を維持できる
既存顧客の評判や口コミもビジネス戦略に組み込めるため、顧客との関係性を維持できる効果が期待できます。従来のビジネスモデルでは、獲得した見込み客が再度顧客として商品やサービスを購入してくれることは少なかったです。
いわゆるリピート率が低い状態で、安定的な収益が見込めませんでした。ただしフライホイールを導入することにより、既存顧客との信頼関係を築ければリピートにつなげられます。新規顧客を獲得さえできれば、継続的な収益が期待できます。
フライホイールが必要な企業
フライホイールは、基本的にどのような企業でも通用するビジネスモデルです。情報が溢れる現代において、顧客の環境やニーズは日々進化しています。これまでは営業が直接顧客にアプローチするのが一般的でしたが、マーケティング部門からコンテンツを発信するほうが効果的な場合も多いです。新規顧客の獲得やリピート率の改善に課題を抱える企業であれば、フライホイールの導入がおすすめです。
Amazonのフライホイール成功事例
フライホイール効果をビジネスに取り入れ、劇的な成長を遂げた代表例がAmazonです。
世界中で利用されるオンラインショッピングプラットフォームとなり、今や生活に欠かせない存在となっています。
Amazonの「フライホイールモデル」は、創業者のJeff Bezosが「Flywheel Effect」として社内に提唱したものであり、HubSpotのマーケティング用フライホイールとは独立した概念です。ただし、いずれも「成長を加速させる循環モデル」である点は共通しています。
- 低コストの仕組み化
- キャッシュフローの最大化
- 成長モデルへの投資
低コストの仕組み化
Amazonは1994年に設立され、1995年にオンライン書店としてサービスを開始しました。
当初から「低価格で商品を提供することで顧客満足度を高める」戦略を取り、これがリピート購入を生み出し、取扱量の増加へとつながりました。
商品量が増えることでスケールメリットを得て、さらに低価格を実現。この好循環がフライホイールを加速させ、急速なビジネス拡大を支えたのです。
また、豊富な商品ラインナップによって、競合との差別化にも成功しました。
キャッシュフローの最大化
Amazonのビジネスモデルの大きな特徴は、利益ではなくキャッシュフローの最大化に重きを置いていることです。
単に利益を追うのではなく、安定したキャッシュフローを確保することで、設備投資や新規事業への挑戦に積極的に取り組める体制を築いています。
もちろん、これまでに参入した新事業のなかには、大きな失敗に終わった例も少なくありません。
しかしAmazonには、「可能性があるならまず挑戦すべきだ」という文化が根付いています。たとえ多くの失敗があっても、成功する事業がひとつ生まれれば十分に取り返せる、という発想です。
この挑戦を恐れない姿勢こそが、Amazonをあらゆる分野で成長させてきた原動力となっています。
成長モデルへの投資
Amazonはフライホイール効果を高めるために、成長モデルへの投資をおこなっています。数多くある投資の中には残念ながら失敗に終わった挑戦もありますが、新事業が生まれているのも事実です。ここでは、実際に成功した興味深い事例をいくつか紹介します。主な成功事例は、次のとおりです。
- Amazon GO
- Amazon Launchpad
- 物流業界への参入
Amazon GO
Amazonが新たな試みとして開発したのが、完全無人型のデジタル店舗「Amazon GO」です。
この店舗では、これまで当たり前だった「レジでの支払い」が一切不要となり、画期的な買い物体験を提供しています。
利用者は、専用アプリを使って入店ゲートでQRコードをスキャンし、あとは店内で欲しい商品を選んでそのまま店を出るだけ。
商品を手に取る動作や持ち出しを、店内に設置されたカメラやセンサー、AI技術がリアルタイムで認識し、自動的に購入データを記録します。
店を出ると、登録済みのAmazonアカウントに対して決済が行われ、購入内容もアプリ上で確認可能です。
万が一、誤認識や返品が発生した場合でも、アプリから簡単に手続きができる仕組みになっています。
この「Just Walk Out Technology(ジャスト・ウォーク・アウト・テクノロジー)」によって、レジ待ちや支払い手続きの手間を完全になくし、顧客満足度を大幅に向上させました。
Amazon GOは、未来の買い物体験を先取りする店舗モデルとして、世界中から大きな注目を集めています。
Amazon Launchpad
Amazon Launchpadは、スタートアップ企業による新製品の市場投入を支援するプログラムです。
自由な発想やストーリー性を持った革新的なプロジェクトを対象に、Amazonが市場試験やプロモーションをサポートします。これにより、消費者はインターネットを通じて、簡単に新しい製品を購入できる仕組みになっています。
このプログラムの目的は、Amazonプラットフォーム上で取り扱う商品の幅を広げ、より多様な顧客ニーズに応えることにあります。
個性的で他にはない商品が数多く並ぶことで、利用者に新たな購買体験を提供し、顧客満足度の向上にもつなげています。
物流業界への参入
これまでAmazonは、自社商品の配送を外部の大手物流業者に委託してきましたが、現在は自前の配送ネットワーク構築に本格的に取り組んでいます。
その一環として進めているのが、「Shipping with Amazon(SWA)」と呼ばれる独自配送サービスの展開です。
このサービスが軌道に乗れば、将来的には自社商品だけでなく、他社商品の配送も請け負うことが可能になり、Amazonが物流業界においても大きなプレイヤーになる可能性があります。
さらに、各家庭への配送手段としてドローンの活用も視野に入れており、ドローン配送技術の特許取得も積極的に進めています。
これらの新しい試みにより、配送スピードや利便性を向上させ、最終的にはAmazonユーザーの満足度向上を目指しています。
なお、Amazonの成長戦略の根底には、「低コスト」「豊富な品揃え」「優れた顧客体験」という考え方があり、これは創業者ジェフ・ベゾスが描いた「フライホイール効果」のメモにも明確に示されています。
フライホイール効果を高めるポイント
フライホイールは、さまざまな分野で役立つビジネスモデルです。うまく導入できれば、ビジネスの成長へと役立てられます。ただし、導入方法ややり方を間違えると期待した効果が得られないことも多いです。フライホイール効果を高めるポイントには、次のようなものがあります。
- 新しい技術を取り入れる
- 失敗を恐れず行動に移す
新しい技術を取り入れる
IT技術は日々進化しており、新しい技術が生まれています。競合他社との差別化を図るためにも、新しい技術への関心を高めておくことが大切です。常にアンテナを張り情報を取得することで、新たな発想が生まれることもあります。また新技術への関心を深めるだけでなく、新たな事業に参入する際に積極的に取り入れることが求められます。
失敗を恐れず行動に移す
新技術への関心を深め、アイデアを生むだけではビジネスは成長しません。実際に行動することで初めて意味を成すため、失敗を恐れずに行動に移すことが大切です。失敗を恐れて守りに入る企業も多いですが、守りの姿勢では新しい事業は生まれません。
海外では失敗に寛容な企業が多いですが、日本は失敗を責める傾向があるので良いアイデアが生まれても行動に移さないことも少なくないです。技術革新が阻害されやすい環境であるため、企業が率先して挑戦しやすい空気感を作ることが求められます。
まとめ
 インターネットが普及する近年は、企業が発信する情報より第三者の口コミや評判が購買意欲に影響を与えているといわれています。このような状況下で従来のビジネスモデルを続けていても、企業が抱える課題を解決することはできません。フライホイールの概念を確認したうえで、見込み客やリピーター客を取り込める施策を打つことが大切です。
インターネットが普及する近年は、企業が発信する情報より第三者の口コミや評判が購買意欲に影響を与えているといわれています。このような状況下で従来のビジネスモデルを続けていても、企業が抱える課題を解決することはできません。フライホイールの概念を確認したうえで、見込み客やリピーター客を取り込める施策を打つことが大切です。